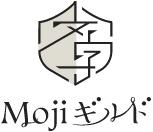【第1話】 はじめまして、アイです
「はい、タカハシ企画です!あ、いつもお世話になっております!え、追加ですか?はい、わかりました、いつもありがとうございます!」
「……はぁー」
電話を切ったアカネは、思わず溜息を漏らしてしまった。
無理もない、先月から依頼が急増していてまともに休日を取れていないからだ。
アカネは小さな制作会社でWebライターをしている。
まだ入社して1年なので、日々の仕事をこなすだけで精一杯。
「ん?アカネ、どうした?」
オフィスに戻ってきたミツルがアカネに問いかける。ミツルはこの会社でディレクターをしている。メガネをかけ、優しそうな面持ちが特徴的だ。
「せーんぱーい…またA社のコラム記事の追加が入りました…」
普段は明るくて元気いっぱいなアカネも、さすがに疲れがピークに達している。
ミツルも徹夜することが増えているし、アカネの大変さはよくわかっていた。
「俺も倒れそうですよ…」
ボソッとテツヤが呟く。
テツヤはあまり仕事熱心とはいえないが、この忙しさで連日残業をこなしていた。
「うーん、こう毎日仕事が増えると、流石にしんどくなってくるな…」
3人で天井を見上げていたところ、突然オフィスのドアが開く。
「おー、みんなお疲れ!!なんだ、元気がないなー!はっはっはっ」
やってきたのはこの会社の社長、タカハシだ。
「社長、お疲れ様です。また仕事の追加が入って、流石に僕たちだけじゃ持ちませんよ…」
普段は陽気なタカハシも、この時ばかりは真剣な顔でミツルの話を聞いていた。
「そうか、仕事量のことは俺に任せてくれ。近いうちに解決しよう!!」
それだけ言い残し、タカハシはどこかへ行ってしまった。
「社長、何しに行ったんですかね?」
アカネが首を傾げながら言った。
「さぁ、俺にもわからん。とりあえず、もう少し仕事頑張ろうぜ!!」
そう言って、3人はまた仕事に打ち込んでいった。
それから5日後、珍しく朝からタカハシが出社していた。
「みんな、おはよう!今日は新しい仲間を紹介しよう!さ、入って入って」
タカハシの声につられるように、1人の女性が部屋に入ってきた。
「今日から一緒に働いてくれるアイさんだ、よろしくな!」
「はじめまして、アイです」
ミツルはアイをじっと見て、あることに気がついた。そう、アイが全く瞬きをしていないことに。
「社長、もしかしてこの女性は…」
「流石ミツル君だな、もう気がついたか。そう、このアイさんは新型のアンドロイドだ」
2040年の日本では、人型ロボットのアンドロイドと人間が共に働く機会が増えている。しかし、それは倉庫や製造業などの単純作業が多い現場での話だ。
「でも、ウチはクリエイティブな会社ですよ?アンドロイドに仕事をお願いするのは…」
「はっはっはっ。アイさん、試しにこの記事を作成してくれないか?」
ミツルの意見に対しタカハシは直接答えず、アイに指示を出した。
「わかりました」
アイは企画書を手に取ってパソコンの前に座ると、勢いよく執筆を始める。
本来、ライターが記事を書く際には情報を集め、整理し、記事にしていく。
しかし、アイは情報を整理せずに直接執筆を始めてしまったのだ。
なめらかなタイピングで執筆を続けるアイに、3人は注目する。
30分ほどして、アイが作った記事が完成した。
事前のリサーチをしなくても、必要な情報が盛り込まれていていい記事になっている。
「なるほど、確かにいいね」
これで、今の忙しさが落ち着くかもしれない。
そう考えて、ミツルとアカネは目をキラキラさせ、テツヤはホッと息をついた。
「アイさん、アカネくんの隣を使ってくれ。わからないことがあったら、ディレクターのミツルくんが何でも答えてくれるから安心してね!それじゃ私は失礼するよ」
タカハシはそう言ってまたどこかへ消えた。
そもそも、彼はクリエイターではない。だから、どんなに忙しくても彼自身が仕事を手伝ってくれることはない。
「みなさん、よろしくお願いします」
アイは深々と頭を下げながら言った。
「こちらこそよろしくお願いします。その、僕たちはアンドロイドと仕事するのが初めてで…。何か失礼があったらすいません」
アイは何も答えず、3人をじっと見つめていた。
(こういう時、アンドロイドって何を考えているんだろう。ちょっとドキドキするな)
ミツルは頭を搔きながらそう考えていた。
「そうだ、アイさん。仕事を始める前に、ウチの会社のことを知ってもらった方がいいね」
ミツルの提案に、アカネも同意する。
「そうですね、アイさんには私たちの職場や仕事の流れを知ってもらわないと」
その隣で、テツヤはジッとアイを観察していた。
「僕は仕事してるんで、2人に任せますね」
そう言って、テツヤはデスクに戻っていく。
2人はまず、職場を案内した。
小さな制作会社なので、部署などはない。休憩室とデスク、トイレがあるだけだ。
「ここがライターの席で、隣がディレクターの席です。そして、あまり使っていないけどあっちに社長の席があります」
タカハシのデスクには書類が山積みになっていた。
基本的に会社にいないので、承認が必要な書類がどんどん溜まってしまう。
「すごい書類の山ですね。皆さんいつも忙しいのですか?」
「そうなんだ。この業界、常に納期に追われて大変なんだよね」
ミツルが苦笑いしながら話す。アカネもつられて苦笑いした。
アイは2人の表情を見て、不思議そうな顔をした。
一通り案内を終えて雑談した後、4人で早めの昼食を取ることになった。
「いつも、この近くのラーメン屋に行くんだ。美味しいからオススメだよ」
「そうそう!あっ、でもアイさんって食事するのかな…?」
アカネが疑問を口にすると、アイは微笑んだ。
「私も食事できますよ。ただ、栄養を摂るためではなく、人との交流を楽しむためですけどね」
「それは良かった!じゃ、僕たちと一緒に行きましょう」
行きつけのラーメン屋に入ると、いつもの店主が4人を出迎える。
「おっ、いらっしゃい!おや、今日は見慣れない人がいるね」
「はい、今日からウチで一緒に働くアイさんです」
ミツルがアイを紹介すると、店主は驚いたような表情を見せた。
「そうか、アンドロイドの方が働き始めたのか。時代は変わったもんだねぇ」
店主はアイをじっと見つめながら話した。
席に着くと、4人はそれぞれラーメンを注文した。
程なくして、出来立ての美味しそうなラーメンが運ばれてくる。
「いただきます!」
ミツルとアカネが声を揃えて言うと、アイも「いただきます」と言った。
テツヤは静かにラーメンを口に運ぶ。
「私、ラーメンを食べるのは初めてなんです。画像でした見たことがなくて…」
「アイさん、今まで食事はどうしていたの?」
アカネは口をもぐもぐしながらアイに尋ねる。
「人間のように食事をしたことはありません。内蔵バッテリーが減ってきたら充電します」
「羨ましいなぁ。ってことはそのスタイルもずっとキープできるんでしょ?私なんて最近…」
アカネはお腹を触りながら語尾を濁した。
「確かに、見た目は基本的には変わりません。依頼主の希望によって、多少見た目を変えることはありますが」
「ん?どういうこと?」
「なかにはアンドロイドだと隠したがる人がいるので、そういう依頼主の場合は髪型を変えたり、肌を変化させたりします」
「そうだったんだ。アンドロイドも大変なんだねぇ」
アカネが返事をした後に、これまで静かだったテツヤが口を開く。
「でも、アンドロイドなら疲れることもないんですよね?いいなぁ…」
「きっと、僕たちの大変さもわからないでしょう?アンドロイドと働くなんて、僕は嫌ですね」
テツヤは目を伏せながら言った。
「ちょっと、アイさんに失礼じゃない!謝りなさいよ!」
アカネがちょっと強く言うと、テツヤは体を丸めた。
「テツヤさん、私のせいでごめんなさい。でも、私には断る権利がないの。その分、みなさんが少しでも楽になるように、仕事がんばりますね。」
アイは静かに伝えたが、テツヤは目を背けたままだ。
「ねぇねぇ、アイさんはどうしてウチの会社で働くことになったの?」
アカネが場の空気を変えるために質問を投げかけると、アイはゆっくりと話し始めた。
「私は人間と交流することが好きなんです。前はアンドロイドだけが集まる工場で働いていましたが、人間と一緒に働きたいと思うようになって。
契約が終わってしばらく待機していたんですが、そこにタカハシさんから注文が入ったんです。
クリエイティブな仕事は初めてですが、事前学習は一通り終えてきたので、みなさんと一緒に良いものを作りたいです」
アイの言葉を聞いて、ミツルとアカネは安心した。
「そっか、アイさんも一生懸命がんばろうとしてくれているんだね」
「うん、みんなで力を合わせれば、きっといい仕事ができるよ」
ラーメンを食べ終わった後、4人は店主に挨拶をしてお店を出た。
「さーて、今日はここまで片付けよう!」
「はい、みなさん、よろしくお願いしますね」
アイが頭を下げると、ミツルとアカネも微笑んだ。テツヤは何も答えず席に移動する。こうして、アイを迎えた初日はコツを教えつつノルマを無事に達成できた。
アイはわからないことを隠さず聞いてくれるので、思った以上に呑み込みが早いのは嬉しい誤算だ。
「じゃ、お疲れ様です」
仕事が終わるとテツヤは静かに挨拶をし、先にオフィスを出る。
「あぁー、こんなに早く帰れるのはいつぶりだろう…」
アカネの安堵する声がオフィスに響いた。
「俺も今日はゆっくり晩酌できそうだよ、アイさん、本当にありがとうね」
「いいえ、明日からもよろしくお願いいたします」
「よろしくね、それじゃお疲れ様でした」
残った3人もオフィスを後にし、それぞれの家に帰っていく。
帰りの電車の中で、ミツルは考え事をしていた。
(人間よりも知識が豊富なアンドロイドに、どうやって指示を出していけばいいんだろう。そう遠くないうちに、俺の知識じゃ太刀打ちできなくなる)
仕事が進むようになるのは嬉しいが、ミツルにとっては難しい立ち回りを迫られることになったのも事実だ。
(俺ももっとアンドロイドについて知っていかないとな。テツヤのこともあるし、何かあった時にアイさんをサポートできなくなる)
イヤホンから流れてくる音楽が、ミツルの脳内を虚しく通過していった。
ー第2話へ続くー