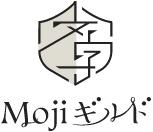夢
高層ビルの最上階にある自宅の窓から、東京の夜景を見下ろしていた。
無数の光が瞬く街並みは、まるで自分の頭の中を駆け巡る思考のようだ。
ここが最上階であるという事実は、これが現実だと感じるための道具でしかない。
コトバが有限になった世界。
この現実が、俺をここまで連れてきた。
25歳で「人のためになる仕事がしたい」と起業したこの会社は、3年であっという間に大きくなった。
幼い頃から、人と話すのが好きだった俺にとって、営業、プレゼン、プロモーションは得意分野だった。事業に投資してくれる会社を探すことも、業績を上げることも、想定していた以上にスムーズに進んだ。
とんとん拍子に業績が伸び、自分のコトバが金になると自覚してからの俺は、やり手の若手社長として名をあげることになる。
休みなく働いているが、充実した毎日だ。会社をもっともっと大きくしたい。
そのためなら、いくらでもコトバをつかう覚悟がある。
徐に、机の引き出しから古ぼけた日記帳を取り出す。幼い頃に書いていたものだ。ページをめくると、無邪気な夢や希望が綴られている。
「夢は叶ったんだよな」
東京の街に飲み込まれるだけのコトバを使ったって、誰からも咎められることはない。
親友
チャットの通知音が、俺の思考を現実に引き戻した。画面には、親友で副社長の拓也からのメッセージが表示されている。
拓也:明人、明日の投資家向けプレゼンの最終確認だ
明人:もう資料はできてる。30分後にオフィスで
拓也:了解。お前のコトバが聞けるのが、楽しみだ
拓也とは、かれこれ15年の付き合いだ。
一緒に起業しようと言い出したのは拓也の方だった。
大学の論文発表で、俺のコトバ力を見抜いたらしい。
俺のことを誰よりも信じてくれた、大事な親友だ。
「お前のコトバ力と、俺の知識があれば、たくさんの人を幸せにできる」
酒を飲む度に二人で日本一について熱く語っていたし、「二人なら日本中の人を幸せにできる」本当にそう思っていた。
「よう、明人。今日も遅くまで働いてるな」
「お前もな。時間ないからサッサとやろうぜ」
話題を仕事に向け、パソコンの画面を拓也に向ける。
しかし、拓也は椅子に深く腰掛けると、真剣な表情で俺を見つめた。
「その前に、少し話があるんだ」
眉をひそめる。拓也のこの表情は、何か重大な話がある時にしか見せない。
「なんだ?問題でも?」
「ああ、問題と言えば問題かもしれない。明人、…」
一瞬、言葉を失う。拓也の真剣な眼差しに、反論の余地はなさそうだった。
「拓也、どういうことだ?」
「お前、最近コトバ代を使いすぎじゃないか?確かにビジネスには必要だ。でも、利益を考えて、もっと効率的にできないのか?」
拓也の言うことは理解できる。利益を生み出さなければ、事業は運営できない。
でも俺は立ち止まれない。コトバを使って、会社をもっとでかくしたい。
「拓也、俺はとにかく会社をでかくしたい。今はコトバ代を惜しんでる場合じゃないだろ?」
「わかってるよ。でも、焦りすぎてないか?このままじゃ会社もお前もパンクするぞ」
言葉を飲み込む。拓也の指摘は痛いほど的確だった。
「わかった。考えてみる」
静かに答える。拓也はほっとしたように笑顔を見せ、話題を明日のプレゼンに戻した。
自宅に帰ってきたのは、夜か朝かわからない時間だった。
窓の外に見える東京の街も、寝ているのか起きているのかわからなかった。
(最近ぐっすり寝たのは、いつだったかな?)
一瞬そんなことを考えたが、すぐに明日のプレゼンの準備を始めた。頭の中にあるコトバの海を泳ぎながら、正解を探し続ける。眠ったかどうかは、どうでもよかった。
転機
朝日を眩しいと感じるようになった頃には、頭の中では今日のイメージトレーニングは完璧にできていた。
身だしなみを完全な状態に整え、プレゼンに向かう。今日の投資家向けのプレゼンが成功すれば、新しいプロジェクトを動かすことができる。
しかし、到着した会議室には異様な雰囲気が漂っていた。
「どうしたんだ?」
問いかけると、秘書の臼井が青ざめた顔で近づいてきた。
「社長…どうしてここに?」
「どういう意味だ。今日はプレゼンの日だろ」
「…まだニュースをご覧になっていないのですね?」
臼井が差し出したニュースの見出しを見て、一瞬目の前が真っ暗になった。
【大手〇〇社社長が辞任】
「…なんだって?」
声が震える。何が起きているのか全くわからなかった。
頭が追いつかないまま、次に入ってきた文字が脳を大きく揺らした。
【次期社長には、現副社長の櫻井拓也氏が就任】
「もう限界だったんだよ、明人」
後ろから聞こえた拓也の声に、ゆっくりと振り向いた。
「……どういうことだよ。俺は辞任するなんて一言も言ってないぞ」
「適当にサインするからだろ。書類の手続きは全部終わってる」
「全く意味がわからない。なんでこんな…」
「お前の経営には、もうついていけないんだよ。社員のみんなも同じ意見だ。こんなに会社がでかくなったっていうのに、社員の暮らしは全然よくならない」
「でも!それでも救えるお客様は確実に増えてる!俺のコトバで会社をでかくして、日本中の人を幸せにするんじゃないのかよ!」
「…明人。お前についてきたみんなの幸せ、考えたことあんのかよ」
その言葉に息を飲んだ。
「…明人のおかげで会社がでかくなった。そのことには感謝してる。でもな、俺は社員のみんなを幸せにしてやりたいんだ」
ーそこから、どうやって自宅に帰ってきたのかは覚えていない。
なにも言えなかった。会社がでかくなれば、誰かを幸せにできると信じて必死で働いてきた。自分のコトバが、誰かを救うと信じて疑わなかった。
どうすればいい?何を言えばいい?
初めて、自分を信じられなくなった。これまで信じてきた「コトバの力」が、全て嘘のように思えた。
「俺のコトバで、幸せにできるんじゃなかったのかよ…」
言い放ったコトバは、だれにも届かなかった。
コトバと幸せ
あれからどのくらいの時間が経ったのかも、わからなくなっていた。
東京の街で、がむしゃらに働いてきた日々が、嘘のように何もすることがなかった。
「実家に帰ろうかな…」
そんなことを思いながら、引き出しにしまった古い日記をぱらりとめくった。
日記と呼べるほど立派なものではないが、昔から思ったことや感じたことを書き留めておくのが習慣だった。
その中でも特に大切にしている言葉がある。
“ぼくの言葉は人をしあわせにする”
子どもの頃から、自分の心を満たしてくれる大切な言葉だ。
幼い頃に両親が離婚し、母と二人で裕福とは言えない生活を送っていた。
母親は毎日遅くまで働いていて、一人で過ごす時間が長かったので、寂しくなかったと言えば嘘になるが、不幸だと思ったことは1度もない。
夜遅くに帰ってきた母親と、今日何があったか、どんなことをして過ごしたかを話しながら寝るのが、幸せな時間だと思っていた記憶がはっきりと残っている。
「明人のお話は、いつもママを幸せな気持ちにしてくれるね。ありがとう」
話が終わると、母は必ずこう言ってくれた。
自分の言葉が母を幸せにするという事実が、心から嬉しかったのだ。俺の言葉力の高さは、母との思い出によって作られている。
それは会社が大きくなった時、確信に変わった。
”俺の言葉は人を幸せにする”
これまで、コトバこそがすべてだと信じてきた。
あの時の母の笑顔、あの時くれたありがとうの言葉。
社員の笑顔とありがとうの言葉を、ちゃんと見たことがあっただろうか。
拓也は、いつもどんな顔をして働いていたんだっけ。
「言葉で人を幸せにする…か」
少しずつ、思考がクリアになっていくのを感じる。
「よし、やってみるか」
朝日が登ったのを見たとき、当たり前に眩しいと感じた。
幸せにする言葉
「明人くんおはよう」
「おー。優奈さんおはよう。膝の調子どお?」
「かなり調子がいいのよ。今から文さんとお散歩に行くの」
「無理しないようにね!いってらっしゃい」
自分よりも年上の友人と、今日も挨拶を交わす。
コトバが有限になったこの時代、収入がなくなり孤独な生活を送っているお年寄りは多い。
だが、俺の暮らすこの街は、お年寄りのコトバ代は税金で賄われている。
おかげで老若男女、誰とでも挨拶が行き交う、いい街だ。
会社をやめてから、東京から少し離れたこの街で暮らすことを決めた。
“明人の言葉は人を幸せにする”
この言葉と、もう一度真っ直ぐに向き合うためだ。
この街は、コトバ代が無料で使えることに感謝の気持ちを持っている人が多い。
だからこそ、言葉の使い方は暖かく、ポジティブだ。
(昔の人は、こんな風に言葉を使ってたのかな。幸せだったんだろうな)
草むしりをしながら、そんなことを考えていると、後ろから声をかけられた。
「町長さん」
「…拓也」
顔を合わせるのはあの日以来だった。
相変わらず田舎町が似合わないので、思わず笑ってしまった。
「会社、うまくいってるな。たまにニュースで見るくらいだけどさ。さすが拓也だよ」
「おかげさまでな。明人こそ、まさか町長になって街をつくってるなんて。コトバ代無償の街ってメディアで取り上げられてるの見て、驚いたよ」
「簡単じゃなかったけどな。俺に会いにきてくれたのか?」
「まあな」
そこからは、お互いに言葉を飲み込んだ。
あの時、俺は会社を大きくすることに必死だった。
それが間違っていたとは、今でも思っていない。
実際に、会社のサービスや事業は成功し、今でも多くの顧客をかかえ、拓也の経営手腕もあって上場企業になった。
拓也が、そんな俺を嫌いになったわけではないことは、俺が一番よくわかっていた。
周りが見えなくなった俺を、ずっとそばで支えてくれたのは拓也だったんだから。
「拓也。会いにきてくれてありがとう。あの時、俺のこと止めてくれなかったら、俺の言葉は人を幸せにする言葉じゃなくなってたと思う」
言葉にしないと、伝わらないことがある。
「嫌な役やらせて、ごめんな」
伝えないと、癒えない痛みもある。
「形は違うけど、俺たち二人とも、人を幸せにできてるよな?」
聞かないとわからないことがある。
「おれがこの街をつくるまでの苦労と努力、聞いてくれる?」
話したいと思える人がいる。
言葉を使って人を幸せにする方法は1つじゃない。
拓也は少し恥ずかしそうに笑って、いつもの調子で答えた。
「了解。久しぶりにお前の言葉が聞けるのが、楽しみだ」
ー第2話 終ー
この記事を書いたライター

Nishino
アパレル業界一筋15年。2人の子どもを育てる副業ライター。現在はシナリオライティングをメインに活動中です。おもしろいことが好き!おもしろい人が好き!そんな自分の「好き」を伝えられるライターになりたいです。いえ、なります。
夢は開業...