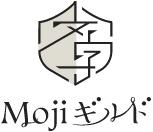わからない、自分の気持ち
「ほら、俺が言った通りじゃん。明見久遠はムジカになりきってタクミに恋をするよ、って」
しずるがストローでアイスコーヒーをせわしなくかき混ぜながら言った。
どうやらこれは彼のクセらしい。
「制作発表会見の明見久遠の言葉も話題になったでしょ。あれも、彼らしいなと思ったもん」
しずるの言葉に勝利の胸がドクンと波打った。
明見久遠の初BLドラマとあって、ドラマの制作発表会見の会場には大勢の報道陣が詰めかけた。
会見ではまず第1話の試写会が行われ、その後、監督・脚本家・プロデューサー、そして俳優陣が一言ずつ、ドラマへの思いについて述べていった。
大木監督からマイクを渡された明見が静かに話し始めた瞬間のことを思い出すと、勝利の胸は締めつけられるような思いになる。
でも、同時になぜか甘く心地よい感覚も覚えるのだった。
「…僕はこのドラマの台本を読んで、恋愛に対する考え方が180度変わりました。つまり、自分自身の恋愛対象は、女性だけではないのだな、と気づいたんです」
わかっている。決して明見は「宮田勝利が恋愛対象である」と断言したわけではない。
わかってはいるけれど、その言葉を聞いたとき、なぜか勝利の心は踊った。
「ねぇ、あの明見久遠の発言、どう思う?」
勝利はあの時の気持ちを思い起こしながら、しずるに聞いた。
「なにが?」
「ほら、あの『自分の恋愛対象は女性だけではない』って発言。結構話題になったじゃん」
「あぁ、あれか」
しずるはそっけない態度で続けた。
「ありゃ、一種のリップサービスでしょ。これからBLドラマに出る俳優が、『BLドラマには出ますが、自分の恋愛対象は女性です』なんて事前にエクスキューズしてたら、視聴者が感情移入できないじゃん。明見久遠にぬかりがない、ってだけだよ」
「…そっかぁ」
高ぶる思いに冷や水をかけられたような気がして、勝利は椅子の背もたれに勢いよくもたれかかった。
なんだか興ざめだ。
しずるなら一緒に「意味深な発言だよね」って興奮してくれると思ったのに。
運ばれてきたときのクリームソーダは美しいエメラルドグリーンだったのに、勝利がアイスクリームをすべてソーダ水に溶かしてしまったせいで、すっかり濁ってしまった。
自分のせいなのに、誰か他の人にやられたかのように不満げな表情で目の前の飲み物を見つめる勝利。
そんな勝利の表情に気づいたしずるは、小さくため息をつき、続けた。
「あのね、勝利。俺が最初に言ったこと、覚えてる?『明見久遠は全身で恋する気持ちを勝利にぶつけてくるけど、それは明見久遠としてじゃないよ。ムジカとしてだよ』って」
「わかってるよ」
勝利は汗をかいたグラスから視線を外すことなく答えた。
そんなのわかってる。
何度も繰り返し自分に言い聞かせているし、事あるごとにしずるの声でその言葉が頭の中で聞こえていた。
そして、それがすごく邪魔で不快だったんだ。
「じゃあ、そこら辺のマスコミやSNSで騒いでいるファンと同じように、明見久遠の言動に翻弄されないことだよ。明見久遠が見つめているのはタツキだよ。明見久遠の視線の先に、君はいない」
しずるの容赦ない言葉に胸がズキッとした。と同時になぜだか腹が立った。
「そんなのわかってるよ。なんでそんな、俺が明見久遠に惚れられてる、ってうぬぼれてるみたいな感じで話すの?ただ、どう思う?って言っただけじゃん」
「そう?それならいいけど。ちょっと舞い上がってるのかな、と思ったからさ。それは俺が心配しすぎたね。ごめん」
しずるは口論へと発展するのを避けるべく、自分が折れることを選んだ。
「…なんか俺もごめん。ちょっとネガティブに受け取りすぎたかも」
しずるの思いがけない謝罪に、勝利も自分の大人げのなさを反省した。
そして心のどこかで、「もしかしたら、明見久遠は勝利に惚れてるんじゃない?」なんて言われるんじゃないか、と期待していた自分を恥ずかしく思った。
なんとなく白けた空気になったので、2人は解散することにした。
店の外に出出た勝利は、肌をほんの少しだけヒリつかせるような眩しい日差しに夏の名残を感じた。
「俺、タクシー拾うから」
サングラスをかけながらしずるが言った。
「仕事?」
「いや、猛さんとメシ食いに行くの。俺、来週から映画のクランクインだからYouTubeにしばらく付き合えないよ、って言ったら、じゃあメシ食いに行こう、って」
「ふ~ん。気に入られてるじゃん」
「まあね。でも、なんだかんだ言って今日の様子もYouTubeにアップするんじゃない?」
しずるはにっこり笑ってそういうと、通りかかったタクシーに手を挙げた。
「じゃあ、あと少し撮影がんばってね」
そう言ってタクシーに乗り込むしずるの背中に勝利も声をかける。
「しずるも映画、がんばってね」
「まかせとき~」
手を振るしずるを乗せて去っていくタクシーを見送った後、勝利は駅に向かって歩き出した。
「どうしたの?機嫌悪いじゃん」
清原猛は運ばれてきた生ビールを喉をならしながら美味そうに飲みほすと、口元を拭いながら向かいの席に座っているしずるにたずねた。
「…なにが?」
目の前のサラダをフォークでつつきながら、しずるが答える。
2人はイタリアンレストランの個室で差し向かいに座っている。
ミシュランにも掲載されたこの店は、完全予約制のうえ全席個室なので、芸能人がよく愛用することで知られている。
洞窟をモチーフにしているという店内は少し薄暗く、天井が低い。
モルタル調の塗り壁など、内装にこだわっている感が「いかにも」業界人が好きそうな店だな、としずるは思った。
もう秋口だというのに水色のポロシャツにホワイトのハーフパンツにスニーカーという出で立ちの清原は、まるで夏が過ぎてしまったことを認めたくないようだ。
しかし、日焼けした肌にそのスタイルがよく似合うのも事実だ。
清原は、チェシャ猫のように大きな口を横に広げ、にやりとしたまま身を乗り出し、しずるにささやいた。
「宮田と喧嘩でもしたか」
「はぁ?」
まんざら嘘でもないため、強く否定できないしずるは、そういうのが精一杯だ。
「だってお前今日、昼間は宮田に会う、って言ってたじゃないか。いつも宮田に会ったときは上機嫌なのに、今日はテンション低すぎ。だったら宮田と喧嘩した、と考えるのが普通だろ」
「…まあね」
ここまでお見通しなら仕方がない。
しずるは腹をくくって清原に愚痴り始めた。
「なんか、あいつ、浮かれてたから。俺があれだけ『明見久遠は役柄に入りきってるだけだからね』ってアドバイスしてあげたのに、てっきり明見が自分に気がある、と思い込んでるの」
「なんだ嫉妬か」
思いもよらない清原の言葉に、しずるはさっきとは違うテンションで「はぁ?」と声に出した。
テーブルを訪れたウエイターに空のビールジョッキを渡し、代わりにハイボールの入ったグラスとピザを受け取りながら清原は続けた。
「面白くないんだろうよ。あいつがそうやって、他の男の言動に一喜一憂している姿をはたで見ているのが」
一応人物名を出さない配慮はしているらしい。
ウェイターがその場を離れたのを見届けると、清原は言った。
「お前、自分で気づいてなかったの?自分が宮田に惚れてること」
しずるはジントニックを2口飲んでから、こう呟いた。
「…俺は、恋している自分が嫌いなの」
「ん?」
「最初は会えるだけでいい、話せるだけで幸せ、って思ってても、だんだんと欲深くなって、自分だけを見てほしい、自分だけを愛してほしい、って思うようになって。かといって何か特別なアクションをするわけでもなくうまくいかなければ、それを自分の境遇や相手の周りにいる人間のせいにして。で、そんな自分にますます自己嫌悪。俺の恋愛ってその繰り返し」
ピザの皿に手を伸ばし、一片をつまみながらしずるは続ける。
「だからね、俺は恋をしないの。これ以上自分を傷つけたくないから」
「…惚れた腫れたは不可抗力だろうよ。自分の意思でどうこうできるもんでもないぜ」
清原の言葉に、しずるは頬を膨らませた。
「もう、そんなこと言うんなら帰ろうかな。楽しくないや」
清原は大きな声で笑いながらグラスを掲げた。
「ごめんごめん。まぁ、機嫌を直せよ。映画撮影の間、つかの間のお別れなんだから、今日は楽しくやろうよ」
一方勝利は、自宅に戻り、ベッドに寝転んで撮り溜めていた「星から来た彼」を見ていた。
自分の演技に自信を無くしたくないから、クランクアップを迎えるまでは見ないでおこう、と思っていたのだが、気が変わったらしい。
********
翌日の土曜日、タツキは昼過ぎに目覚めた。ムジカはまだ寝息を立てている。
タツキは彼の長いまつげを見るともなく見ていた。
閉じたまぶたの下で眼球が2~3回動いたあと、ゆっくりとムジカは目を開けた。
タツキと目が合うと、にっこりと笑う。それはまるで、目覚めて一番に母親の姿を認め、安心した赤ちゃんのようだった。
ムジカが目覚めるまでは「今日こそは警察に行こう」と思っていたタツキだったが、その笑顔を見ると、なんだかその気が失せてしまった。
「ムジカさん、メシ食いに行きましょうか」
タツキがそういうと、ムジカは「はい」と嬉しそうに笑った。
********
勝利はドラマを見ながら撮影風景を思い出していた。
本当は2人並んで歩くシーンのはずなのに、明見はそっと手を握ってきた。
驚いて明見の顔を見ると、彼はムジカのほほ笑みでこう言った。
「昨日は、こうやって歩きました」
胸の鼓動が明見に聞こえるのではないか、と勝利はハラハラした。
でも、そのハラハラがなんだか心地よかったのも事実だった。
********
タツキとムジカが一緒に暮らし始めて1週間がたった。
タツキが仕事に行っている間、ムジカはずっと映画を見ている。
タツキはムジカが本当に宇宙人なのかもしれない、と思い始めた。その理由はいろいろある。
まずは、あまりにも世間を知らなすぎること。
テレビをつけると画面の向こうに人が移っていることに驚いていた。
ガスコンロの火に興味を持ち、触ろうとしたこともあった。
それに、真夏なのにコート姿で暑いだろう、とタツキのシャツとパンツを着せる、寒い、と震え出すのだ。
そして、一番不思議なのが雨に打たれても、お風呂に入っても、髪の毛も体もまったく濡れないこと。
まるで撥水シートのように、水滴をはじいているのだ。
毎日ムジカに驚かされながらも、その反面タツキはムジカに惹かれていくのを感じていた。
仕事から帰ると、「会いたかった」と抱きついてくるムジカ。
フライドポテトが大好きでお腹がすくとすぐに「フライドポテトを食べましょう」というムジカ。
昼間に見た映画の話を目を輝かせてしてくれるムジカ。
一番お気に入りの映画は「ローマの休日」だというムジカ。
仕事で疲れたり凹んだりして帰ってきたときは、何も話さず黙って寄り添ってくれるムジカ。
そんな彼と一緒にいると、なぜか心が休まり、元気になれるのだった。
********
撮影が進むにつれて、勝利は明見と目が合う回数が増えたな、と感じるようになった。
撮影現場でどれだけ人がいても、なぜか必ず明見の姿は見つかるのだ。
そして勝利が明見の姿を見つけると、必ずと言っていいほど明見も勝利に気づく。
明見は少しほほ笑むときもあれば、軽く手を上げて挨拶してくれることもある。
缶コーヒーを一緒に飲んで以来、明見とじっくり話せる機会はなかなか持てなかったが、勝利は明見が自分の存在を気にかけてくれていることを実感していた。
そしてそれがとても嬉しかったのだ。
しかし、勝利は気づいていなかった。目が合う回数が増えたのは、必ず明見の姿を見つけられたのは、勝利が無意識のうちに明見を目で追っていたからなのだ、ということに。
ー第7話へ続くー
この記事を書いたライター

大中千景
兵庫県生まれ広島在住のママライター。Webライター歴8年、思春期こじらせ歴○十年。SEOからインタビューまで何でも書きます・引き受けます。「読んで良かった」記事を書くべく、今日もひたすら精進です。人生の三種の神器は本とお酒とタイドラマ。