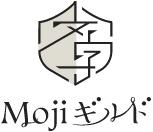【第8話】君のことが知りたい
「あんた。目が赤いんだけど。今日インタビューだけじゃなくて撮影もあるって言ったよね」
車で勝利の家まで迎えに来た叶は、助手席に座った勝利の顔を見るや否や、少しイラつきながら勝利に言った。
「…ごめん。ちょっとゲームしすぎて」
嘘だ。
1週間ぶりに明見に会えると思うと、胸が高鳴って眠れなかったのだ。
叶はシートベルトを外すと体をひねって後部座席に手を伸ばし、トートバッグを乱暴につかむと、中を開いた。
出てきたのは使い捨てのホットアイマスクだ。
「付け焼刃だけど、スタジオ着くまでこれあてときなさい」
助手席のシートを倒し、ホットアイマスクを目の上にのせた。
叶が静かに車を走らせる。
視覚がさえぎられたぶん、聴覚が研ぎ澄まされる。
FMラジオから流れる音楽の歌詞がクリアに耳に飛び込んできた。
ーねぇ、きっとこれから君は僕のことを、もっと好きになるよ
この曲は「エモーショナル・キッス」だ。
ーだから僕は、ありったけの想いを込めて、君にキスしよう。唇から愛が伝われば、君はもう、離れられないよ
アイドル時代のフワフワした明見の笑顔に続いて、ドラマの最後の撮影シーンが勝利の脳裏に浮かんだ。
明見の唇の感触が鮮明に蘇ってくる。
「やべ」
勝利はいたたまれなくなってアイマスクを外し、慌ててシートを上げた。
「何よ。変な夢でも見てたの?」
勝利の返答を待つことなく、叶は続けた。
「これ、明見久遠のアイドル時代の曲よね。あのときはキュートな男の子って感じだったけど…。ほんと、彼って脱アイドルのモデルケースのような存在よ。プロ意識の高さには目を見張るものがあるわ。勝利、2作目にして彼と共演できて、しかもドラマ撮影が終わった今でも一緒に仕事できるなんて、ラッキーよ」
「ラッキー、かぁ」
勝利はそう言って、気持ちを切り替えるべく伸びをして、事前に雑誌社から送られてきた質問状に目を通した。
インタビューは明見が指定したスタジオの一室で行われた。
明見は「星から来た彼」の撮影が終わるやいなや、休む間もなく主演映画の撮影がスタートしていたため、雑誌社のスタッフと勝利が、映画の撮影を行うスタジオへと足を運ぶ流れになったのだ。
インタビューに使用される部屋の中央には簡易テーブルと椅子が置かれ、卓上にはペットボトルのお茶が用意されている。
明見と勝利は隣同士に座り、その向かい側にインタビュアーが腰かけた。
今回インタビューを受ける雑誌は、男性に人気のファッション誌『contigo(コンティーゴ)』。
明見は白のTシャツにカーキのシャツを羽織り、ボトムスは黒のワイドデニム、という出で立ちだ。
一方勝利はショート丈の白のジャケットにベージュのワイドパンツ。
あまり着なれないファッションなので、なんだか居心地が悪い。
それもそのはず、今回のコーディネートはすべて叶が選んだものなのだから。
「すいません。僕の方で場所指定しちゃってわざわざ来ていただいて」
と明見が開口一番、謝罪をすると、インタビュアーは「とんでもない」と顔の前で右手を激しく左右に振った。
「主演映画の撮影で忙しいときに、お時間をいただき、こちらこそ感謝しています」
インタビュアーは茶色のパンツスーツに身を包んだ、笑顔がチャーミングな女性だった。
年齢は叶と同じくらいだろうか。スムーズな話の進め方からして、相当場数を踏んでいるようだ。
彼女の進行のおかげで、インタビューはテンポよく進む。
「今回のドラマを通じて、お互いの仲というか、絆は深まりましたか?」
インタビュアーの質問に間髪入れず明見が答える。
「実は、宮田くんと、プライベートでまだゆっくり会話できていないんですよね。僕、撮影中は自分の世界に閉じこもりがちというか、あまり共演している方と話すタイプじゃないんで」
明見はそう言うと、優しくほほ笑んで勝利の方を見た。
「でも、ドラマでの2人のケミストリーは、自分でいうのも何だけど、最高でした。だから…これからもっと宮田くんのことを知っていきたいな、と思っています」
勝利の手のひらに一気に汗が噴き出た。
顔に熱を感じる。赤面していることを明見に気づかれませんように。
「明見さんのこの言葉を聞いた宮田さんのお気持ちは?」
しどろもどろになりながら勝利も答える。
「そうですね。僕も、明見さんと共演できてすごく幸せで嬉しかったから、これからもっと明見さんのことを知れたら嬉しいです」
愛の告白だと思われたらどうしよう。
そう思うと、なかなかうまく言葉が出てこない。
「では、これからも2人の共演作が期待できる、ということですか?」
インタビュアーが続けた。
すると明見は少し間をおいて、言った。
「…今僕たちは、あすみやとして注目されていますが…それが宮田くんの足かせになっていないか、と心配しています。彼は本当にいい役者です。だから、もっと大きく羽ばたいてほしい。あすみやの宮田勝利では終わってほしくないんです」
勝利は胸がチクチク針で刺されるような気持ちになった。
そうか。明見はあすみやとしての仕事がこの先も続くことを望まないんだ。…俺とは違って。
「でも、これからもあすみやとしてのオファーがある限り、僕は喜んで受けますよ。だって、宮田くんとはもっと一緒に仕事がしたい」
明見の言葉を受けて、勝利は思わず口を開いた。
「僕は、あすみやの仕事…仕事っていうほどたくさんのことはしていないけど、でも、明見さんと一緒にいる時間が好きです」
さっきまでは愛の告白だと思われたらどうしよう、なんて心配していたくせに、今度は少しでも自分の思いを届けたいと思う。
なんで1分1秒ごとに気持ちが移り変わるのだろう。
インタビューは20分ほどで終わった。叶と共に帰宅しようとする勝利を明見が椅子から立ち上がって呼び止めた。
「宮田くん」
「…はい」
ふいに呼び止められたときは、どんな表情で返答するのが自然なんだろう。笑顔?真顔?
「ちょっと時間ある?」
「はい、あります。麗さん、いい?」
叶が腕時計を見ながら答えた。
「次の雑誌のグラビア撮影まで、まだまだ時間あるわ。明見さん、大丈夫ですよ」
コーヒーでも飲みに行くから、終わったら電話して、と勝利に言い残し、叶は出かけた。叶が部屋を出たのを見届けると、明見はいたずらっぽく笑った。
「今日の俺の撮影は、終わったんだ。この後も撮影があるっていうのはね、嘘。宮田くんと2人で話したくて」
「え?」
心臓が激しく波打つ。
まったく、明見久遠のせいで、俺は心臓発作で死んでしまうかもしれない。勝利は真剣にそう思った。
「俺のマネージャーにもね、ちょっとやりたいことがあるから、取材は同行しなくていいよ、って言って、撮影終わりで帰ってもらったの。どっか移動する時間も惜しいし、このままここでちょっと喋らない?」
2人で缶コーヒーを飲んだあの日以来、勝利は明見に聞きたいことがたくさんある、と思ったのに、いざとなると、どれも聞く勇気が出ない。
嬉しいような、気まずくて今すぐこの場から逃げだしたいような、不思議な気持ちだ。
「やっとゆっくり話せるね。といっても、そこまでゆっくり、というわけにもいかないだろうけど」
先ほどのインタビューのときに座っていた椅子に再び腰かけ、明見が言った。そして、どこに座ったらいいのかわからず、立ち尽くしている勝利に対し、視線で向かい側の椅子に座るよう促した。
「あの…明見さん、ひとつ聞いてもいいですか?」
椅子に座ると同時に、勝利は意を決して聞いてみた。
「なに?」
「あの、『星から来た彼』、明見さんがタツキ役に俺を指名してくれたって聞いたんですけど…ほんとですか?」
「あぁ、ほんと」
明見はあっさり認めた。
高鳴る胸を抑えながら、勝利はさらに質問を重ねる。
「えっと…なんでですか?」
明見は勝利の目を優しく見つめて、こう言った。
「一緒にやりたかったからだよ」
勝利は顔が真っ赤に染まっていくのを自覚して、慌てて目を伏せた。
「君は覚えてないだろうけど、春の特番で、初めて俺たち出会ったんだよ」
明見はテーブルの上に置かれたペットボトルのお茶を手に取り、ラベルをはがしながら語り始めた。
特番のことはよく覚えている。
春と秋の番組編成が大きく変わる「改編期」に放送されるバラエティで、新番組の出演者が集まりクイズやゲームにチャレンジして賞金獲得を目指す、という内容だ。
勝利は「初恋ノスタルジア」チームとして出演。
子どものころからよく見ていた名物番組に出演できることに、少なからず興奮し、張り切っていたのだ。
結果、大した活躍もできなかったが、芸能界に入ってからの楽しい思い出のひとつとなっていた。
「あの特番、俺も出てたんだよね」
もちろん知っている。明見は勝利の斜め前に座っていた。
明見も春に放送されるドラマの出演者チームとして参加し、アーチェリーやビリヤード対決にチーム代表として駆り出され、期待を裏切らない結果を出していた。
勝利はしずると、「やっぱりスターは違うよね」なんてささやき合っていたのだ。もちろんあのときは、明見と共演する機会があるなんて、ましてや彼に恋をするなんて、全く思っていなかった。
「あのときさ、宮田くんすごく周りに気を使っているな、って思って。共演の子が手で顔をあおいでたら『大丈夫ですか?暑いですか?』って声をかけてたよね。それにADが横を通るたびに『ありがとうございます。お疲れ様です』って挨拶して。なんか素人っぽい子だな~と思ってたの」
そんな風に明見に見られていたなんて、恥ずかしくなって勝利はうつむいた。
「そしたらなんか面白くなってさ。『この子、4時間ずっといろんな人に気を使いっぱなしなのかな。いつ挨拶とかやめるかな』って。そう思ったらずっと観察したくなって。隙を見ては後ろをチラチラ見てた。見てると君、ほんっと楽しそうだったのね」
今度ははがし終えたラベルを小さく折りたたみながら、明見は続ける。
「すげーな。楽しそうでいいな。見てるとハッピーになれるな、って思って。宮田勝利に興味を持った。で、デビュー作のドラマ『初恋ノスタルジア』を見てみたら…」
明見は勝利の目をじっと見る。
今までも明見と見つめ合ったことはある。
でもそれは、ムジカとタツキとして、だ。
勝利は息をのんだ。
明見の瞳の奥は、どこまでも優しい。
「びっくりした。そこには特番ではしゃぐ宮田勝利の姿はなかった。大人しくて姉思いの、一人の物静かな青年がいた」
「ありがとうございます…」
「そのときに、君のことがもっと知りたいと思ったんだ。俳優として。それと…」
「はい」
「ひとりの人間として」
「でも…顔合わせのときとか、全然目も合わせてくれなかったから…俺、嫌われてるのかと思ってて」
「あぁ」
明見はほほ笑んだ。
「だってさ、俺が宮田くんを指名した、っていうことが知れ渡っているのに、そのうえ俺があの場で宮田くんに嬉しそうに話しかけてたら、宮田くんが変に嫉妬されてもいけない、と思ってね」
なんだか勝利は泣きそうになった。
こんなにも俺のことを見ていてくれて、気にかけてくれていたんだ。
そのとき、勝利のスマホの着信音が鳴った。叶からだ。
「タイムオーバーだね」
明見は立ち上がり、小さく折りたたまれたラベルをダストボックスへと投げ込みながら呟いた。
「すいません…」
なぜか謝ってしまった勝利に、明見は言った。
「全然。話せてよかった」
叶からの電話はやはり、「そろそろ時間だ」と告げるものだった。
「じゃあこれで…」
と立ち去ろうとする勝利に、明見が言う。
「ねぇ、電話番号教えてよ。俺のも伝える」
パンツのヒップポケットからスマホを取り出しながら明見は続けた。
「さっき、インタビューでも話したでしょ?君のことを、これからもっと知りたいんだ」
ー第9話へ続くー
この記事を書いたライター

大中千景
兵庫県生まれ広島在住のママライター。Webライター歴8年、思春期こじらせ歴○十年。SEOからインタビューまで何でも書きます・引き受けます。「読んで良かった」記事を書くべく、今日もひたすら精進です。人生の三種の神器は本とお酒とタイドラマ。