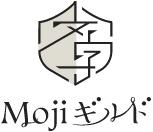【第9話】スマホの向こう
「…それで俺に電話してきたの?」
電話の向こうのしずるは、少々ぶっきらぼうな口調だった。
そうとは気づかず勝利は話を続ける。
明見の思いを聞いたこと、連絡先を交換したこと、最初は自分の胸の内にとどめておくつもりだったが、どうしてもしずるには聞いてもらいたくて、電話をかけたのだ。
本当は「これって両想いってことだよね?」とストレートに聞きたかったが、それではあまりにも無粋な気がして、「どう思う?」というふんわりとした質問に切り替えた。
「…わかんない」
しばしの沈黙の後、しずるは答えた。
「えぇ~なんでだよぅ。しずる、恋愛経験豊富そうだから、聞いてみたのに」
Tシャツにボクサーパンツ姿の勝利は、スマホを左耳に押し当て、ベッドの上で仰向けに寝転んでいる。
「俺はそんなに恋愛経験豊富じゃないよ」
しずるは苦笑して続けた。
「どう思う、って気になってるってことは、勝利は明見久遠に恋しているの?」
今度は勝利がしばし沈黙する番だった。
「…たぶん、そんな気がする」
「そっかぁ!」
突然しずるが大声を出したので、勝利は「うわ、びっくりした」と呟いた。そんな勝利に構うことなくしずるは語り始める。
「いいじゃん。恋を知らなかった男・宮田勝利の初恋の相手が、あの超人気俳優、明見久遠だなんて、ドラマよりもドラマティックだね」
「…なんか楽しんでないか?正直言うと、本当にこれが恋なのかどうかはわからないんだよね。でも、明見さんのこと考えると、なんか前向きになれるというか、人生って素晴らしいな~って思えるんだよね。そういう存在がいるってことが、俺、嬉しい」
しずるは、少々勝利の弾む声が耳障りに感じた。これ以上会話を続けていると、勝利を傷つける一言を言ってしまいそうだ。
「そう思えるって幸せだよ。まぁ、がんばってみなよ。影ながら応援しておく。明日も早いから、俺、そろそろ寝るわ」
「あ、ごめん。まだロケ中?」
「そう。今はね、兵庫県の淡路島にいる。1週間になるかな?日帰りの温泉があるから、時間あるときは通ってるよ。来週にはようやく帰れそう」
「そっか~がんばってね。帰ったらまたシャンティに行こうよ。おやすみ」
「おやすみ」と言ってしずるは電話を切り、スマホをベッドの上に放り投げるとベランダに出て夜風にあたった。
風の中にほんのり海のにおいがする。最初は窓の向こうに見える鳴門海峡と大鳴門橋の景観に感動したが、3日もたつと慣れてしまった。
しずるはその見慣れた風景をぼんやりと眺めながら、勝利との出会いを思い出していた。
ドラマ「初恋ノスタルジア」の顔合わせのとき、勝利は、ガチガチに緊張した面持ちでしずるの隣に座っていた。
その姿があまりにも可哀そうだったので、彼の緊張をほぐすべく、声をかけた。
「宮田勝利くんだよね?俺、高山しずるです。宮田くん、モデルしてたよね?雑誌でよく見てたよ」
不安で潤んでいた勝利の瞳にみるみる光が差し、はじけるような笑顔が生まれた。「あぁ、いい笑顔だな」と思ったことは覚えている。
「わぁ、高山さん。はじめまして!俺、高山さんのドラマめっちゃ見てました!よろしくお願いします!」
屈託のない笑顔で握手を求めてくる勝利。
もしかしたらあの瞬間から、俺は勝利に恋をしていたのかもしれない。
でも、自分ではそれを認めたくなかった。
撮影現場でしずるの姿を見かけるたびに、嬉しそうにほほ笑む勝利が、自分の気持ちを知った瞬間に心を閉ざすのが怖かった。
撮影が進むにつれ、勝利との距離も縮まり、いつの間にかお互いの名前を呼び捨てするほどの関係になっていた。
ーそれでいい。それでじゅうぶんだ。だって、俺は勝利のことを友達として好きなだけで、恋しているわけではないから。友達なら、ずっと勝利の大切な存在でいられるから。
必死に自分にそう言い聞かせていたのに。
なんで今、死ぬほど辛いんだろう。
夜風に当たりすぎたらしい。
白のロングTシャツにグレーのスエットという寝間着姿では少々寒い。
しずるは部屋の中へと戻った。
ふと、ベッドの上に放り投げられたままのスマホに視線を落とす。
しずるはスマホを拾うとベッドの端に腰掛け、電話をかけた。
「おぅ!しずる!久しぶりだね。どうした?俺に会えなくて寂しくなったか?」
「逆だよ。猛さんが俺に会えなくて寂しがってるんじゃないかと思って電話してあげたの」
電話の向こうの清原は大笑いして「大正解!電話くれてめちゃくちゃ嬉しい!」と答えた。
ー俺は最低だな。
しずるは清原の優しい声を聞いていると、罪悪感で死んでしまいたくなった。
ー猛さんのこと、全然好きじゃないのに。
でも、清原なら絶対に優しくしてくれるとわかっていてしずるは電話した。誰かに優しくしてもらいたかった。
誰かに愛されている、という自覚を持ちたかった。
たったそれだけの理由で。
ーだから、恋をする自分は大嫌いなんだ。
「どうした?元気ないな。撮影、ハードなのか?」
顔が見えないのに、声のトーンだけで、清原はしずるが本調子じゃない事がわかるらしい。
「あ、ごめんごめん。ちょっと疲れてるのかも」
「疲れてるときに俺を思い出してくれて嬉しいよ」
温かい清原の言葉に涙が出そうになった。
ー猛さん、ごめんね。
そのころ、勝利はベッドに寝ころんだままスマホの画面とにらめっこしていた。
待ち受けにしている実家のパグ犬・ジョンに語りかける。
「ねぇ、ジョン。俺、明見さんに電話していいのかな」
実は連絡先を交換してから1週間がたつが、明見からは何の連絡もない。
最初の3日間は、いつ連絡があるか気が気じゃなく、スマホを肌身離さず持っていた。
入浴中もフリーザーバッグの中にスマホを入れて、バスタブの側に置いていた。
仕事の合間にあまりにも細かくスマホをチェックする勝利を叶が「恋人でもできたの?」といぶかしんでいたくらいだ。
次の3日間は、不安が勝利を襲った。
ーもしかして俺、連絡先間違えて教えたとか?
ー連絡先交換したいっていうのはただのリップサービスだったのかも。
ーもしかして、もう恋人がいるのかも。あれだけの大スターなんだから、極秘で恋人がいてもおかしくないよな。
…次から次へと浮かび上がる懸念事項に、たまらず勝利は
「ねぇ、俺ってネガティブ思考の天才かも」
と叶に漏らした。
「は?何があったのかはわかんないけど…。もう少し自分に自信を持った方がいいかもね。今はまだ、いい意味で素人臭い部分があって、それが魅力だけど、この先それが足を引っ張りかねないからね。永遠のアマチュアでいるつもりなのかはわからないけれど、ちゃんと明見久遠みたいに大人の男へとイメチェンしないと、人気も急降下よ」
勝利の一言がきっかけで、なぜか叶に説教モードが入ってしまったため、この後15分ほどお小言が続いてしまった。やぶへびだ。
それからまた1日が経過。
連絡先を交換して1週間たった今日、たまらず勝利はしずるに電話をしたのだ。
もし、しずるが「勝利と明見は両思いだと思うよ」と太鼓判を押してくれたのなら、意を決して勝利から明見に電話をかけようと思っていた。
しかし、しずるの返事はどうとも取れないものだった。
「もしかしたら、俺が恋愛モードに無理やり持って行ってるだけで、明見さんにとっては仕事仲間とのフツーの会話なのかな」
コチラを見ているジョンに向かって勝利が呟くと、スマホの画面が突然光り、着信音が鳴った。
画面には「着信 明見久遠」と表示されている。
勝利は目を閉じて深呼吸を2回すると、「通話」のボタンをタップした。
「ごめん。寝てた?」
明見の優しい声が聞こえると、なんだか胸がいっぱいになった。
「いえ。あの…」
「ん?」
「実は俺も、電話しようかな~なんて思ってたんです」
「そっか。それは嬉しいな。あれからすぐに電話しようと思ったんだけど、ロケが始まってなかなか時間が取れなかった」
「じゃあ今は、東京にいないんですか?」
「うん。今はね、広島にいる」
「広島!遠いなぁ」
「そうだね。でも…」
「でも?」
「宇宙にいるよりは、ずっと近い」
不思議なもので、勝利は明見の声を聞いていると、ふたりが両想いかどうかなんてどうでもよくなってきた。
ただ、明見と話をする時間、会える時間をひとつひとつ大切に積み重ねていけるのなら、それでいい。
「広島はどうですか?俺、行ったことないや」
「いい街だよ。お好み焼き、美味いしね。川が多くて、川沿いにはずっと木が植えられているから、景色もいい。早朝に散歩すると、気持ちいいよ」
「へぇ~行ってみたいな」
「いいね。一緒にまた来よう」
「今の言葉、録音しとけばよかった。絶対ですよ」
特にふたりの関係を明確にするような会話が行われたわけではない。
明見から期待を持たせるような言葉をかけられたわけでもない。
でも、他愛のない会話がなんでこんなに心地いいんだろう。
ー昨日の食事の話
ー天気の話
ー今の仕事の話
話したいことが次から次へと溢れだす。
それもくだらないことばかり。
明見の存在が耳元から全身へと広がっていく。
勝利は今まで味わったことのないような幸せを感じていた。
願わくば、ほんの少しでも、明見も同じ感情を抱いてくれていますように。
30分くらい話していただろうか。明見が
「じゃあ、そろそろ切るよ」
と告げ、パーティーはお開きとなった。
本当はもっと話していたかったけれど、ぐっとこらえて勝利は答えた。
「すっかり長電話になっちゃって、ごめんなさい」
嘘だ。全然長くなんて感じなかった。
明見とならきっと、夜通しでも話せる。
「また電話する」
という明見の言葉に胸が躍る。
「はい。待ってます」
「おやすみ。勝利」
そういって明見は電話を切った。
突然明見が下の名前で自分を呼んだことに驚きと喜びを感じた勝利は、スマホを耳にあてたまま、ため息をついた。
電話を切る間際の明見の「勝利」という声のトーンは、確かに聞き覚えがあるものだった。
受話器の向こうからは電話が終了したことを告げる「ツーツー」というビジートーンが流れている。
その音を聞きながら、勝利はドラマのキスシーンを思い出していた。
「…私もです。私も大好きです。勝利」
明見はあの時本当にそう言ったのかどうかはわからない。
でも、真実は確かめなくていい。
そう言った、と信じておこう。
そのほうが、ずっと幸せでいられるから。
ー第10話へ続くー
この記事を書いたライター

大中千景
兵庫県生まれ広島在住のママライター。Webライター歴8年、思春期こじらせ歴○十年。SEOからインタビューまで何でも書きます・引き受けます。「読んで良かった」記事を書くべく、今日もひたすら精進です。人生の三種の神器は本とお酒とタイドラマ。