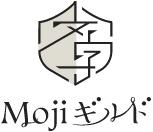主語と目的語の役割とは?

主語と目的語は文章においてどのような役割を担っているのでしょうか。「主語と目的語がないことで文章にどんな影響が出るのか」、「文章におけるそれぞれの役割とは何か」について考えていきましょう。
主語について
まず主語について考えてみましょう。
以下の文章を例に挙げて実際に考えていきます。
斉藤さんがデパートで花を買った。田中さんがその花を上田さんにあげた。
この文章で主語を抜いた場合、「デパートで花を買った。その花を上田さんにあげた。」となります。主語を抜いたことで、誰が花を買ったのか、そして誰が上田さんに花をあげたのか、まったくわからない文章になっています。
また主語を一つ入れたからと言って、意味が伝わるものでもありません。
斉藤さんがデパートで花を買った。その花を上田さんにあげた。
という文章にしたら、読者は花をあげたのが田中さんではなく、斉藤さんが花を買ってそのまま上田さんにあげたのだと捉えてしまいます。
主語は文章の主体を表すため、主語を抜いてしまうと、読者が誰の行動によるものなのか混乱します。主語を加えて、誰についての行動かを明確にすることで、文章を読み進めていく上での迷いがなくなります。
目的語について
目的語の役割についても、主語のときと同様「斉藤さんがデパートで花を買った。田中さんがその花を上田さんにあげた。」という文章で考えていきましょう。
目的語を抜いた文章は以下の通りとなります。
斎藤さんがデパートで買った。田中さんが上田さんにあげた。
この文章を読んでいて、斉藤さんは何をデパートで買ったのか、田中さんは上田さんに何をあげたのか気になります。
また目的語を文章に組み込んだからといって、完全に読者に伝わるわけではありません。
斉藤さんがデパートで花を買った。田中さんが花を上田さんにあげた。
という文章にしたら、読者は花をあげたのが田中さんではなく、斉藤さんが花を買ってそのまま上田さんにあげたのだと捉えてしまいます。
主語は文章の主体を表すため、主語を抜いてしまうと、読者が誰の行動によるものなのか混乱します。主語を加えて、誰についての行動かを明確にすることで、文章を読み進めていく上での迷いがなくなります。
目的語について
目的語の役割についても、主語のときと同様「斉藤さんがデパートで花を買った。田中さんがその花を上田さんにあげた。」という文章で考えていきましょう。
目的語を抜いた文章は以下の通りとなります。
斎藤さんがデパートで買った。田中さんが上田さんにあげた。
この文章を読んでいて、斉藤さんは何をデパートで買ったのか、田中さんは上田さんに何をあげたのか気になります。
また目的語を文章に組み込んだからといって、完全に読者に伝わるわけではありません。
斉藤さんがデパートで花を買った。田中さんが花を上田さんにあげた。
読者はとっさに、斉藤さんが買った花と田中さんが上田さんにあげた花が一緒かどうかわからず、戸惑います。前後の文章のつながりを意識していないと、読者の思考を停止してしまうことになりかねません。
目的語は動作の対象となるものを表しており、目的語がないことで主語の人物が起こした具体的な行動を把握できなくなります。目的語を加えて、主語の人物の行動を明確にしていくことで、読者が文章を読み進めるのに立ち止まることがなくなります。
読みやすい文章をつくる方法3つ
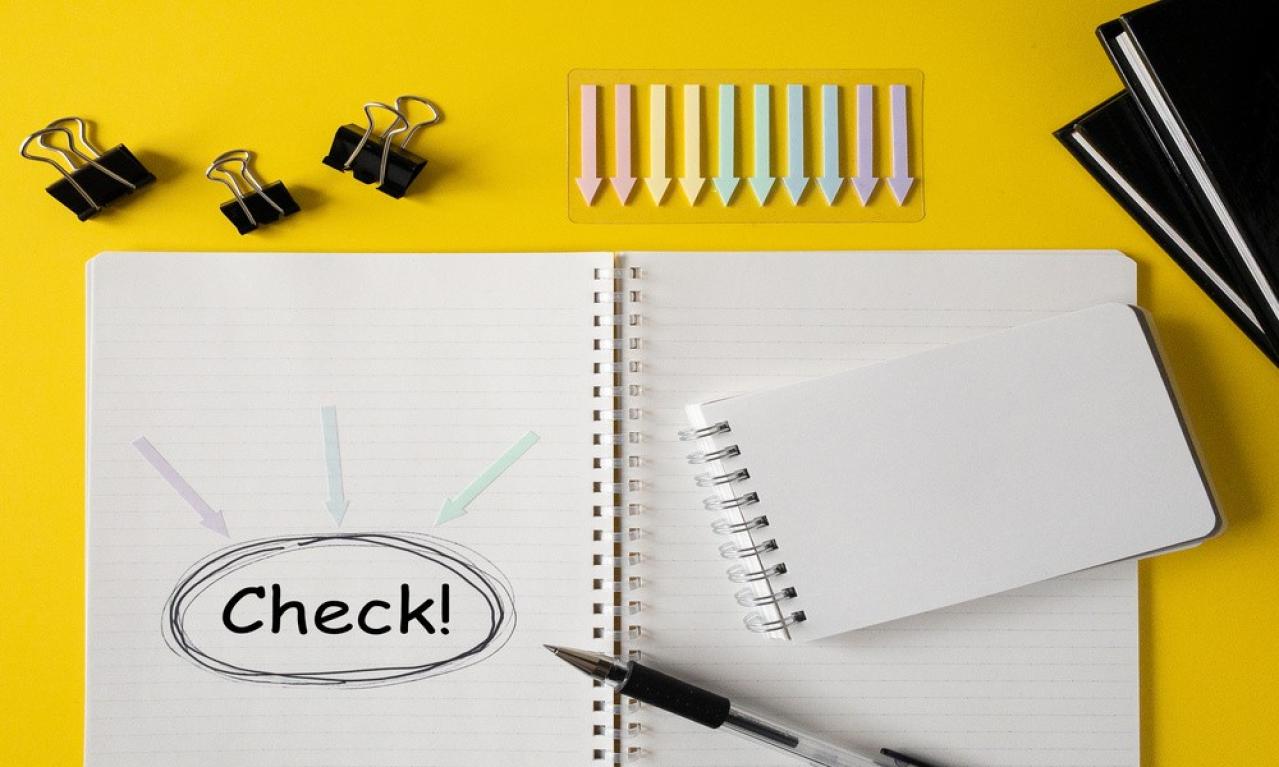
実際に読者が読みやすいと感じる文章を作るにはどうしたらいいのでしょうか。
読者が文章の理解に戸惑わないようにする方法は以下の3つです。
- 基本的な文法を組み込む
- 主語と述語をねじれさせない
- 一文を簡潔にする
それでは、一つずつ見ていきましょう。
基本的な文法を組み込む
文法というと難しく聞こえるかもしれませんが、具体的には「主語、述語、目的語がはっきりした文章」であれば、基本的な文法が組み込まれているといえます。
たとえば、
車が道路を走る。
という文章は、主語・目的語・述語を適切に組み込んでいるため、読者には文章がはっきりと伝わります。しかし、この基本的な文法だけだと味気ない文章になってしまいかねません。基本的な文法で文章を組んだ後に、読者の想像を書き立てる文章に仕立てていくとよいでしょう。
たとえば先ほどの「車が道路を走る」という文章を、
緑の車が海沿いの道路を颯爽と走る。
という文章にしていく形です。「緑の」「海沿いの」「颯爽と」という修飾語を加えたことで、読者の想像力が大きく広がります。
基本的な文法を組み込むことは絶対条件として、修飾語でさらに読者のイメージを掻き立たせる文章をつくっていきましょう。
主語と述語をねじれさせない
主語と述語のねじれとは、具体的に言うと主語と述語がかみ合っていない状態を指します。
たとえば、
私の趣味は、映画をよく観ます。
という文章です。主語の「私の趣味」に対して「観ます」という述語になっているため、読んでいて戸惑う感覚があります。
しかし、この文章を
私の趣味は、映画を観ることです。
に組み替えることで、一気に読みやすくなります。
修飾語や目的語などを入れて文章が長くなる際は、主語と述語のねじれが起きてしまいがちです。ねじれが起きないように主語と述語を対応させるように意識するとともに、文章を書き上げた後に文章を音読することで違和感に気づくことが可能です。
ねじれのある文章は読者にストレスを与えてしまうため、注意しましょう。
一文を簡潔にする
伝えたいことがたくさんあるときは、つい一文が長くなりがちです。しかし、一文が長いと読者は読む意欲が低下してしまいます。
たとえば、以下の文を読んでみてください。
私は明日のドライブが楽しみで1週間前からずっと準備をすすめていたのに、朝になったら土砂降りだったためドライブに行こうか迷っている。
少し長い文章になっているため、読者が文章から離脱する可能性があります。この文章をこのように直してみたらいかがでしょうか。
私は明日のドライブが楽しみで1週間前から準備をすすめていた。 ところが、朝起きたら土砂降りで、このままドライブに行くべきか迷い始めた。
長い文章を2文にすることで、状況がすっきりと伝わります。一文を簡潔にすることで、読者のストレスをなくしていきましょう。
文章はコツを押さえれば、読みやすい文章になる!
読みやすい文章とは「読者に迷いを持たせない、ストレスを与えない文章」です。最初は読みやすい文章が書けなくても、コツさえつかめば誰でも伝わる文章が書けます。
まずは「基本的な文法を組み込む」「主語と述語をねじれさせない」「一文を簡潔にする」の3つを意識して文章を書いてみましょう。
この記事を書いたライター
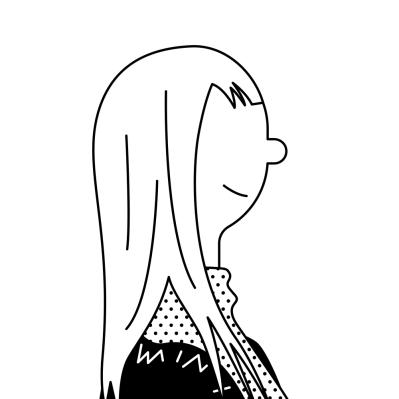
せんゆき
専業Webライター。旅行とキャンプとスイーツをこよなく愛す自由人。金融機関に7年ほど勤めていたものの、より自分らしい生き方を目指すべく退職。現在は自分の好きな場所・好きな時間でライター活動を行っている。読者さんがわくわくするような...