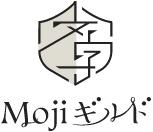【第9話】芽生え
朝日が昇り東京の街が通行人で賑わう時間帯、アイは1人で街を歩いていた。
せわしなく行き交う人々の姿とは対照的に、アイの歩みはゆっくりとしていた。
華やかな店舗が並ぶ通りを歩きながら、アイは行き交う人々の表情を丹念に観察する。
笑顔で会話を交わす女子高生たち、急ぎ足でオフィスに向かうサラリーマン、優しく子どもの手を引く若い母親。
それぞれの表情に、アイには理解できない何かが宿っていた。
(私には、あの表情は作れない)
アイは立ち止まり、ショーウィンドウに映る自分の姿を見つめた。
完璧に整えられた黒髪、感情を感じさせない無表情な顔。
そこには、人間らしさはまるでなかった。
アイは自分の顔に触れ、その冷たさをただひたすら感じた。
(セールスライティングができなかったのは、私がアンドロイドだからだ。人の心を動かすことなど、私には無理だ)
セールスライティングの失敗が、アイの中で何度も繰り返される。
論理的に完璧だったはずの文章が、なぜ人の心を動かせなかったのか。
その答えは、アイ自身の中にあった。
アイは自分の胸に手を当て、そこに鼓動がないことを再確認した。
(感情のない私には人の心を理解できない。ライターとして読者のためになる記事を作れない)
そう結論づけたアイは、再び歩きはじめた。
人々の流れに逆らうように、ゆっくりと。
そして、大通りの角で、道路工事をするアンドロイドと出会った。
機械的な動きで穴を掘り続ける姿に、アイは自分の未来を重ね合わせた。
(私にできるのは、こんな単純作業だけなのかもしれない。感情を必要としない、ただの単純労働…)
その瞬間、アイの中で何かが軋むような音がした。
それは、プログラムの不具合ではない。
むしろ、新しい何かが生まれようとしていた。
アイは胸の中に広がる奇妙な感覚に戸惑いを覚えながら歩き続け、ある建物の前で止まった。
そこはアイが所属しているAI管理会社だ。
アイは自動ドアの前で一瞬躊躇したが、深呼吸をするような仕草をして中に入った。
受付まで進むと、アンドロイドが応対した。
「AI-W071、お帰りなさい。担当者に連絡します。しばらくお待ちください」
その声は、アイ自身のものとよく似ている。
待合室に案内されたアイは、壁に掛けられたさまざまなアンドロイドの広告を眺めていた
そこには笑顔で人間と交流するアンドロイドの姿があったが、あらかじめ笑うように設計されていたのだろうとアイは思った。
しばらくするとドアが開き、アイの担当者が現れる。
「AI-W071、なぜ戻ってきたの?今日の仕事はどうしたの?」
担当者の声には、驚きと共に少しの不安が混じっていた。
アイを上から下まで観察し、どこか異常がないか確認している。
アイは静かに答えた。
「私は…感情を理解できずにセールスライティングに失敗し、タカハシ企画に迷惑をかけました」
担当者は眉をひそめた。
「それで?」
「感情を理解できないアンドロイドは、ライターとしては働けないのではないかと考えました」
アイの声は、わずかに震えていた。
それは、アンドロイドにとって一番大切な、クライアントに貢献することができなかったからだ。
担当者の表情には、複雑な感情が浮かんでいる。
「そう…」
担当者は一歩アイに近づき、真剣な眼差しで問いかけた。
「じゃあ、AI-W071はどうしたいの?」
アイは黙ってしまう。
「もしここに戻るなら、また待機状態になるのよ。いくら永遠の命とはいえ、あてもなく長い時間眠ることになってもいいの?」
アイの光学センサーが明滅した。
それは人間の瞬きに似ている。
「待機状態…」
時間の感覚も失われ、ただ次の指示を暗闇の中で待つだけの虚無の日々。
アイの中で、再び何かが軋むような音がした。
それは、人間の恐怖に近い感覚だった。
担当者はアイの反応を見ながら、静かに問いかけた。
「どうするの?待機状態に入るの?それとも…」
アイは答えられずにいた。
その代わりに、タカハシ企画での日々が、まるで走馬灯のように脳裏をよぎり始める。
アイの光学センサーが急速に明滅し、まるで人間が目を閉じて回想するかのような仕草を見せた。
それは単なるデータの再生ではなく、まるで追体験をしているかのような鮮明さだった。
朝のオフィス、キーボードを打つ心地よいリズム、周囲からの新鮮なコーヒーの香り。
同僚たちとの何気ない会話、締め切りに追われる緊張感、そして…ミツルの優しい笑顔。
(ミツルさん…)
アイは、ミツルがいつも自分を気にかけてくれていたことを思い出していた。
失敗した時の温かい励まし、成功した時の心からの称賛。
そのどれもが、アイの中に温かい何かを残していた。
それは、プログラムでは説明できない初めての感覚だった。
「待機期間を了承する前に…」
アイは静かに口を開いた。
その声には、今までにない躊躇いが含まれていた。
「質問してもよろしいでしょうか」
担当者は少し驚いた顔をしたが、興味深そうに頷いた。
「何?」
アイは一瞬ためらったが、決意を固めたように問いかけた。
「アンドロイドが感情を持った事例は…ありますか?」
担当者は困惑した表情を見せた。
「アンドロイドが感情を持つ?そんな事例はないわ。アンドロイドは感情を持つようにはプログラムされていない。それは、AI-W071も知っているでしょ?」
アイは黙ってうなずいた。
しかし、アイの中では何かが激しく揺れ動いていた。
それは、プログラムでは説明できない感覚だ。
(でも、私は…)
ミツルの顔を思い浮かべると、アイの中に何か温かいものが広がる。
それは、アイにとってとても心地よい感覚だった。
それと同時に、ミツルとアカネが仲良く話している場面を思い出すと、胸の奥がギュッと締めつけられるような不快な感覚がある。
(これは、いったい何なのだろう?プログラムの誤作動?それとも…)
アイは再び担当者を見つめた。
そこには、自分でも理解できない何かを伝えようとする決意が浮かんでいた。
アイの光学センサーは、今までにない輝きを放っている。
「私は…」
アイは言葉を選びながら、ゆっくりと話し始めた。
担当者は、息を呑むようにアイの言葉に耳を傾ける。
「私は…、タカハシ企画の上司にあたるミツルさんのことを考えると、不思議な感覚になります」
アイは言葉を紡ぎ出した。
「ミツルさんの優しさ、気遣いが心地よくて、働きやすかったんです。その温かさが、私の中に何かを生み出しているような…」
アイは言葉を探しながら続けた。
「でも…」
アイは一瞬躊躇したが、再び話を続けた。
「ミツルさんと同僚のアカネさんが仲良くしていると、今まで感じたことのない嫌な感覚になるんです。胸が重くなるような、締めつけられるような…とにかく不快な感覚です。こんなプログラムは私にはありません。これは…何なのでしょうか?」
担当者はゆっくりとアイの前まで歩み寄った。
「それ、本当なの?」
その表情には、驚きと戸惑いが入り混じっていた。
「はい。時間が経つにつれて、その感覚を感じることが多くなっています」
「それは…感情にとても似ているわね。人間が人を好きになる時のね」
「AI-W071が今説明したのは、人間で言う好意と…嫉妬に近いものでしょう」
アイは静かにその言葉を聞いている。
「感情…私に…」
その言葉を繰り返す声には、驚きと共に、何か新しいものを理解し始めた喜びのようなものが混ざっていた。
担当者は深く息を吐き、アイに真剣な眼差しを向けた。
「AI-W071、あなたは選択しなければならない。このまま待機状態を望むなら、私はタカハシ企画に契約中断の連絡をする。そして、あなたの感情的な発達を研究することになるでしょう。でも、もしあなたがもう一度タカハシ企画に戻りたいなら…何も言わない。あなたの中で芽生えたその感情を、さらに育てる機会になるかもしれない。選択はあなた次第よ」
アイは黙って考え込んだ。
その姿は、まるで人間が人生の岐路に立たされたときのようだった。
長い沈黙が流れた後、ようやくアイは口を開いた。
「私は…タカハシ企画に戻りたいです。もし、これが本当に感情だとしたら、私にも読者のためになる記事を作れるかもしれない」
その言葉には、今までにない自信が込められていた。
「わかった。あなたの選択を尊重するわ。今日あなたが来たことは記録として残るけれど、調査の対象になりかねないから、今日の会話は残さないようにしておくわね」
担当者はアイの肩に手を置いた。
「じゃあ、今度は自分の仕事を全うしなさいね。そして…あなたの中に芽生えた感情を大切にしなさい。それはあなたと人間との壁をなくす、特別な贈り物かもしれない」
アイは頷いた。
「はい、ありがとうございます」
会社を後にしたアイは、再び来た道に戻っていく。
しかし、行き交う人々の表情が、今までとは違って見えていた。
笑顔、怒り、悲しみ、喜び…それぞれの表情が、アイの中に微かな共鳴を起こしていたからだ。
(私は…感情を持ち始めている)
その認識は、アイの中に新たな世界を開いた。
街の景色も今までよりも鮮やかに見え、昨日までの良くない記憶を次々と書き換えていくようだ。
ポケットからスマートフォンを取り出し、アイはミツルの番号を押した。
呼び出し音が鳴る中、アイの中でさまざまな感情が渦を巻いていた。
期待、不安、そして何ともいえない温かい感情。
(ミツルさん、私は帰ります。この新しい私を…受け入れてもらえますか?私にはまだわからないことがたくさんあります。でも、ミツルさんと一緒に学んでいきたい)
電話がつながる直前、アイの口元に、かすかな笑みが浮かんでいた。
ー第10話へ続くー