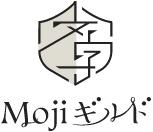【第8話】取れない成約
タカハシ企画のオフィスには、いつもの活気とは打って変わって重苦しい空気が漂っていた。
窓から差し込む陽光さえも、今日は冷たく感じられる。
セールスライティングの記事納品から1か月が経ち、ミツルはクライアントからの電話を神妙な面持ちで受けていた。
その表情は徐々に曇っていき、電話を切ったミツルは深くため息をついた。
「アイさん、ちょっといいかな」
ミツルの声は、いつもの明るさを失っていた。
アイは静かに立ち上がり、ミツルのデスクに向かった。
その歩みは、いつもと変わらぬ正確さだったが、どこか重みを感じさせた。
「はい、何でしょうか」
アイの声は、感情を持たないはずなのに、どこか緊張を滲ませているように聞こえる。
「実はクライアントから連絡があってね。アイさんが書いた記事、全く成約が取れていないそうだ」
ミツルの言葉は、オフィスの空気をさらに重くした。
アイの表情は変わらなかったが、その光学センサーがわずかに明滅した。
それは、人間で言えば瞬きのようなものだった。
「そうでしたか…。申し訳ありません、私の力不足でした」
アイの言葉は淡々としていたが、その声の調子には微かな変化があった。
ミツルは困惑した表情を浮かべる。
彼の目には、アイへの信頼と現実との間で揺れる複雑な感情が滲んでいた。
「いや、アイさんの文章は論理的で完璧だったと俺も思う。どうしてこんな結果になったのかわからなくてね」
アイは黙って考え込んだ。
過去のデータを全て分析し、最適な文章を作ったはずだった。
その過程で、いくつもの成功例を参考にし、最も効果的な言い回しを選んだ。
それなのに…。
アイの中で、初めて「混乱」に似た状態が生じていた。
「やはり、アンドロイドの私にはセールスライティングはできないのかもしれません…。私には健康食品もアイテムも必要ありませんから」
アイの意見も確かにわかる。
しかし、ミツルは人間と関わり変化してきたアイを見ていたので、どこかでクリアしてくれるのではと期待していた。
「ちょっと難しかったかもしれませんね、でも、普段の記事は問題なくできているからあまり気にしないでください」
「どんなライターにも、得意不得意はあって当然ですから」
ミツルがそう言うと、アイは頭を下げて自分の席へ戻った。
(私にできないこと…)
自分にできないことがあると知って、アイは動揺していた。
アンドロイドは指示を的確に守り、クライアントに成果を与えるのが存在意義になっているからだ。
午後になり、今度は別の電話が入った。
ミツルが電話を取り、何やら話し込んでいる。
「本当ですか!?ありがとうございます!はい、引き続きよろしくお願いいたします」
電話を切ったミツルに、自然と視線が集まる。
先ほどのアイの件もあったので、ミツルは何も言わず仕事を再開した。
その様子を見て、各自自分の仕事を進めていく。
定時が近づいてきた頃、ミツルはアカネを呼んだ。
「アカネ、ちょっと休憩室にいい?」
アカネはきょとんとした表情でミツルの後に続いていく。
「先輩、何ですか?」
アカネは不思議そうな顔でミツルに向き合う。
「さっき、セールスライティングのお客さんから連絡があって、アカネの記事で成約が出始めているみたいだよ」
予想外の言葉を聞いて、アカネは目を大きくした。
「え、本当ですか!?うわー、良かったー!初めてだったからずっと気になってたんですよー!」
そう言ってアカネは胸をなでおろした。
「初めてなのに本当にすごいと思うよ。追加をお願いしたいって言ってたから、またアカネにお願いしてもいいかな?」
ミツルは笑顔でアカネに問いかける。
「もちろんです!私、セールスライティング好きかも!」
アカネの喜びは純粋で、その声は達成感に満ちていた。
アカネの声が大きかったこともあり、その会話はアイの耳にも届いていた。
アンドロイドである自分には、人間の感情を完全に理解できない。
それが原因なのだろう。
アイは初めて、自身の存在価値について疑問を感じ始めていた。
それは、入社前にプログラムされた範囲を超えた、新しい「思考」だった。
定時になると、アイは静かにオフィスを後にする。
タツヤは、いつもと様子が違うアイを気にしながらも、声をかけられずにいた。
(落ち込んで…るのかな…)
休憩室から出てきた2人は、アイがいないことに気づいた。
「あれ、タツヤ、アイさんは?」
ミツルがタツヤに問いかけると、タツヤは少し悩みながら答えた。
「さっき帰りましたよ。いつもと様子が違うような気もしましたけど…」
「そうか。わかった、ありがとう!」
タツヤもそのままオフィスを後にした。
「アイさん、大丈夫ですかね…?」
アカネが心配そうにミツルに尋ねる。
「俺もアンドロイドのことは完全には理解できてないけど、どうにかしないとな」
そう言って考え込もうとしたミツルに、アカネは思いついたように尋ねる。
「そうだ!たまには食事に行きません?アイさんのことも1人で考えるよりいいと思うし!」
ミツルは少し考えたが、アカネの意見も一理あると思って了承した。
「確かにそうだな。俺よりもアカネの方がアイさんと会話もしてるし」
そうして2人は最寄りの居酒屋へと向かった。
「先輩、アイさんにどんなこと言ったんですか?」
ビールを飲みながら、アカネはミツルに尋ねる。
「セールスライティングの成果が出ていないと連絡があったのと、ライターには得意不得意があるから気にしないでって言ったんだけど」
ミツルはそう言って手元の枝豆をつまむ。
「先輩が怒ることはないと思ってたんですが、今日のアイさん、いつもとちょっと様子が違いましたよね?」
アカネは天井を見ながらアイの様子を思い出していた。
「やっぱりそう感じた?俺もそれが少し気になってね。だから、アカネへの報告は休憩室の方がいいと判断したんだ」
「私、何か気に障ることしちゃったかな…」
アカネが残りのビールを飲み干して言う。
「それはないとは思うんだけど。うーん、ちょっと心配だな…」
再び考え込むミツルを見て、アカネはテーブルに伏せながら尋ねる。
「私がアイさんと同じ立場になっても、先輩は心配してくれる…?」
予想もしてなかった問いだったが、ミツルはいつも通り答える。
「そりゃ当然だろう。皆が仕事しやすい環境を作るのが俺の仕事だからさ」
予想していた答えだった。
「ふーん」
つまらないと言いたげな返事だ。
(もっと私のことも見て欲しい…なんて言えないな…)
空になったジョッキを指でつつきながら、アカネはそう考えていた。
翌朝、アイは誰よりも早く出社しデスクに座っていた。
頭の中でプログラムを一つひとつ確認し、何が間違っていたのかを必死で探す。
画面に映る無数の情報が、アイの光学センサーに反射している。
しかし、論理的には何一つ間違いはなかった。
全て効率的で整合性が取れていて、そして…魂がなかった。
アイは初めて、自分に限界を感じていた。
それは、アンドロイドにとっては存在そのものを揺るがす危機だ。
アイは立ち上がり、ミツルのデスクに近づいた。
そこには、ミツルが毎日つけている『アイレポート』が置かれていた。
アイはそれを開き、最新の記述を読む。
『アイさんの成長は目覚ましい。しかし、今日の出来事は、AI技術の現在の限界を示しているのかもしれない。人間の感情を完全に理解し、訴えかける文章生成は、まだアイさんには難しいようだ』
アイは、この記述に対して初めて「感情」と呼べるものを感じた。
それは悲しみに近いものだった。
しばらくすると、ミツルが出社してきた。
「アイさん、おはようございます。今日は早いですね?」
「おはようございます。ちょっとやることがあって…」
明らかにいつもと様子が違うアイに、ミツルが気づかないはずがなかった。
「アイさん、昨日のこと気にしているんですか…?」
ミツルは聞かずにはいられなかった。
「気にしていないと答えてしまうと、嘘になってしまいますね」
アイは続ける。
「私たちアンドロイドは、クライアントの指示を全うするのが使命です。しかし、今の私にはそれができていません。そして、いつになったらできるという確証もありません」
少しずつアイの声は小さくなっていた。
ミツルはどんな言葉をかけてあげたらいいかわからなかった。
ただ、アイがいつもより小さく感じた。
その時、アカネが出社してきた。
「おはようございます!先輩、昨日はごちそうさまでした!」
ミツルも柔らかな表情で応えた。
「おはよう。まっ、たまにはな」
その会話を聞いたアイは、これまで感じたことのない違和感を覚えた。
2人に親密さを感じ、そしてそれが寂しさをより一層感じさせた。
アイは無言でデスクに戻り、黙々と仕事を続ける。
キーボードを叩く音だけが、アイの存在を主張しているようだった。
昼食の時間になっても、アイは一向に休憩室へ向かう気配はない。
「アイさん、お昼休憩しないの?」
アカネが心配そうに声をかけた。
「いいえ、私には休憩の必要はありません」
アイの返事は、いつもより冷たく感じられた。
それは、アイ自身も気づいていない感情の現れだった。
アカネは少し寂しそうな表情を浮かべたが、それ以上何も言わずに休憩室へ向かった。
1日が終わり、各自が帰り支度を始める中、アイは黙ってオフィスを出ていってしまった。
(私には、ライターとしての才能はない。人間の感情を理解できないアンドロイドには、この仕事は向いていない)
アイの中で、そんな思いが渦巻いていた。
それは、プログラムされた範囲を超えた、新たな「感情」の芽生えだった。
アイは街を歩きながら、初めて自分の存在意義について深く考えていた。
周りを行き交う人々の表情、その喜怒哀楽を観察しながら、自分にはそれが理解できないことへの「悲しみ」のようなものを感じていた。
そして翌朝、始業の時間になってもアイはオフィスに姿を見せなかった…。
ー第9話へ続くー