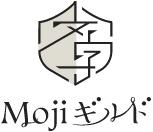【第11話】成長
タカハシ企画には、朝礼をする習慣はない。
しかし、この日は仕事に取りかかる前にミツルが全員を集めた。
大型案件の獲得に成功し、チームで取り組む必要があるからだ。
ミツルは案件の概要を説明していた。
「今回、セールスライティングの大型案件が入った。この案件が継続になると、会社の業績は一気に上向くだろう。皆で協力しながらこの案件を進めていきたいと思っている」
一同は真剣な表情で頷いている。
「そして、アイさん」
ミツルの視線がアイに向けられる。
「はい」
アイは背筋を伸ばして応答した。
「アイさんにもセールスライティングをお願いしたい。今のアイさんなりの感性で、文章を書いてくれませんか?」
アイは一瞬躊躇した。
(まだ私は人間の感情を完全には理解できていない。本当に私にできるだろうか…)
アイの不安を感じ取ったように、ミツルが優しく微笑んだ。
「大丈夫、俺も手伝うし、今のアイさんならきっとできます」
「でも、ミツルさん。私はまだ…」
「アイさんの特別な視点が必要なんです。人間とは少し違うアイさんの感性が、新しい切り口を生み出すかもしれない」
その言葉に、アイは不思議な安心感を覚えた。
「はい、わかりました。精一杯頑張ります」
アイの返事に、アカネも声をかけた。
「アイさん、私も協力するからね!一緒にがんばろう!」
「通常業務は俺が進めておくから安心して」
タツヤも珍しく前向きな様子で言った。
アイは感謝の気持ちを込めて頷いた。
(皆さんの期待に応えなければ)
そう心に誓いながら、アイは自分のデスクに向かった。
(私はこの前の私じゃない)
アイは自分に何度も言い聞かせた。
翌日、アイはアカネに声をかけた。
「アカネさん、少しお話しできますか?」
「もちろん!どうしたの?」
2人は休憩室に向かった。コーヒーを飲みながら、アカネが尋ねる。
「何か悩みごと?」
この前の食事会以降、アイとアカネの仲はさらに深くなって、アカネはよりフランクに話すようになっていた。
アイは少し躊躇いながら口を開いた。
「実は…人間の感情についてもっと詳しく知りたいんです。特に…その…恋愛感情について…」
アカネは少し驚いた表情を見せたが、すぐに笑顔になった。
「へぇ、アイさんも恋愛に興味が出てきたの?」
「セールスライティングを成功させるためにも、人間の感情をより深く理解する必要があると思って」
アカネは少し考え込んでから、話し始めた。
「恋愛感情ってね、相手のことを考えるだけで胸がドキドキしたり、一緒にいるとすごく幸せな気分になったりするかな」
アイは熱心に聞き入っている。
「ドキドキ…幸せ…」
「そう、でも時には切なくなったり、嫉妬を感じたりすることもあるわ」
「嫉妬…それはどんな感情ですか?」
アカネは言葉を選びながら答えた。
「えーっと、好きな人が他の人と仲良くしているのを見て、胸が締めつけられるような苦しい感じかな」
(先輩のことも…)
アカネは自分の気持ちを思い出し、複雑な表情を浮かべる。
「アカネさん?大丈夫ですか?」
アイの声で我に返ったアカネは、慌てて笑顔を取り戻した。
「あ、ごめんね!ちょっと考え事してた」
アイはアカネの表情の微妙な変化を見逃さなかった。
(人間の感情は、本当に複雑だ)
「ありがとうございます、アカネさん。とても参考になりました」
アイはアカネに頭を下げて席に戻った。
デスクに座りながら、アイは考え込む。
(私がミツルさんに対して感じているこの気持ち…これも恋愛感情なのだろうか)
文章を作成する前に、アイは改めて自分の感情に着目していた。
週末、ミツルとアイは揃って休日出勤していた。
アイが抱えるセールスライティングを進めるためだ。
「ふぅ、アイさん、少し休憩しましょうか?」
ミツルの提案に、アイも頷いた。
「そうですね。少し頭を休めましょう」
2人は仕事の手を止め、近くにあるカフェへと向かった。
静かな店内で、ミツルとアイは向かい合って座る。
「アイさん、最近どうですか?感情を持ち始めてから、何か変化は感じますか?」
ミツルの質問に、アイは少し考えてから答えた。
「はい。少しずつですが、新しい感覚を覚えています。嬉しい時、悲しい時、そして…」
アイは言葉を詰まらせた。
(ミツルさんと話すと、胸が温かくなる)
「そして?」ミツルが優しく促す。
「そして、誰かのことを特別に思う気持ち。それが恋愛感情なのかもしれないと思うようになりました」
ミツルは少し驚いた。
「そうですか…。アイさんも、そういう気持ちを持つようになったんですね」
「はい。でも、私にそんな感情を持つ資格があるのかどうか…」
アイの言葉に、ミツルは真剣な表情で答えた。
「アイさん、感情に資格なんて必要ありませんよ。感情はただ、心の中に自然と生まれるものです」
しかし、アイは視線を落としてしまう。
「でも、私はアンドロイドです。人間の方々と同じように感じて本当にいいのでしょうか。嬉しいや悲しいという気持ちを理解できるとライターとして仕事には活かせます。でも、私が恋愛感情なんて…」
人間とアンドロイド、2人が恋愛することが正しいのか、アイには判断がつかなかった。
「アイさんは特別な存在です。アンドロイドだからこそ、人間以上に繊細に感情を感じとれるようになるかもしれません。それを恐れなくても大丈夫ですよ」
アイはミツルの言葉に、何か大切なものを見つけたような気がした。
「ありがとうございます、ミツルさん」
2人の間に、温かな空気が流れる。
(この感覚…これが私の幸せなのかもしれない)
アイはそう思いながら、ミツルの優しい笑顔を見つめていた。
オフィスに戻ったアイは、気持ちを新たにセールスライティングに取り組んだ。
(人間の感情、心の動き…。それを言葉にする)
アイは必死に言葉を選び、文章を紡いでいく。
ミツルは、仕事に打ち込むアイの姿を静かに見守りながら自分の仕事を進めていた。
何か質問があればいつでも相談に乗ろうと考えていたが、アイは自分の経験と感情をもとに少しずつ記事制作を進めていく。
そして翌日、アイが書いた記事の原稿が完成した。
「皆さん、原稿の確認をお願いできますか…?」
アイはミツルだけではなく、アカネやタツヤの意見も求めた。
「いいと思いますよ!フレームワークを丁寧に使っているし、今回は読者の不安や疑問にもしっかり寄り添えています」
ミツルが優しい笑顔でアイに言った。
「私も、読んでいて思ったことを代弁してくれてるなって思った!この記事を読んだら、私も商品を購入してみたくなる」
アカネも自分の感想をそのまま伝えた。
「うん、よくできてると思う。きっと、俺が書くよりも成果につながるんじゃないかな?」
タツヤは頷きながら答えた。
「ありがとうございます、皆さんのおかげでいい記事ができました。あとは結果につながってくれるといいのですが…」
そう、セールスライティングは綺麗な文章を作るだけでは意味がない。
この記事を読んだ読者が、商品を購入してくれてはじめて価値が出る。
「これで先方に提出しますね。すぐには結果はわかりませんが、クライアントからの評価を待ちましょう」
ミツルの言葉に、アイは静かに頷いた。
アカネは嬉しそうに笑うが、その目はミツルを追っていた。
(感情か…。私は…)
アカネの胸に、複雑な感情が渦巻く。
日を追うごとに感情を理解していくアイを見て、アカネは自分に素直になれないことを痛感していた。
ミツルはアカネの視線に気づき、ニコッと笑う。
アカネも応えるように笑った。
(不器用なのはアイさんじゃなくて私の方かも)
アカネはミツルに思い切って言う。
「先輩、今日も祝杯上げちゃいますか?」
この前の食事会の帰り道、自分に素直になれなかったことを後悔していたからだ。
「そうしたいところだけれど、この前も食事会したばかりだしな…」
ミツルは苦笑いしながら答える。
「あっ、そうでしたね!じゃ、クライアントからいい報告が来たらまたやりましょう!」
アカネの言葉に、一同は大きく頷いた。
(その時は、ちゃんと伝えなくちゃ…)
アカネの様子を、アイは静かに見ていた。
(アカネさん…、もしかしてミツルさんのこと好きなのかな…)
アイは、時折、親しげに会話をしている2人を思い出していた。
(もしそうだったら、私は…どうしたらいいのだろう…)
皆が帰宅したオフィスで、ミツルは1人考え事をしていた。
手には『アイレポート』を持っている。
(今度のアイさんの書いたセールスライティング、成果が出てくれるといいんだけれど)
納品した記事が実際に成果につながるかどうかは、ミツルにもわからない。
その時、チャットの着信音が鳴った。
クライアントからのメッセージにはこう書いてあった。
『お世話になっております。先週納品していただいた記事も成約が増えてきました。いつも高品質な記事を納品していただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします』
この記事を担当したのはアカネだ。
アカネはセールスライティングで着実に成果を出し続けていた。
(アカネも立派なライターに成長したな)
クライアントに返信を済ませ、ミツルはパソコンを閉じた。
アカネの入社当時から一緒に仕事をしてきたミツルにとって、今では頼もしいパートナーに成長していた。
特に、アイが入社してからの成長が著しい。
自分の欠点に向き合い、読者に向き合い続けたことでアカネのライティングスキルは大幅に向上した。
(アイさんもアカネも、短期間ですごく成長している)
そして、ミツルはこの前の食事会の帰りの会話を思い出していた。
(感情か…)
ミツルもまた、自分の感情を無視できなくなっていた。
ー最終話へ続くー