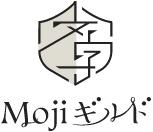【最終話】アンドロイドと人間
アイのセールスライティングを納品してから1か月が過ぎた。
その間、いつも通り慌ただしい日々が過ぎていった。
アイはこれまで通りリサーチをして情報をまとめる仕事をこなしながら、少しずつ人間らしく振舞えるようになっていた。
一番の変化は、笑顔を覚えたことだ。
控え目にクスっと笑うアイは、一見するとアンドロイドだとは思えない。
タカハシ企画の仲間も、アイに新たな変化が起きるたびに一緒に喜んだ。
そこには、命令を与え、仕事をこなすだけの人間とアンドロイドの関係性はない。
そんなある日、1本の電話が入った。
「はい、タカハシ企画です。いつもお世話になっております。はい、少々お待ちください」
「先輩、クライアントからお電話です」
電話を取ったアカネがミツルに対応を促す。
「お電話代わりました。お世話になっております。はい。本当ですか!?」
ミツルとクライアントの会話に一同が自然と聞き耳を立てていた。
「ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします!では、失礼します」
電話を終えたミツルが立ち上がり、皆の視線が集まる。
「アイさん、この前のセールスライティングが商品の購入につながっているとクライアントから連絡がありましたよ!」
アイは目を大きく開いて両手で口を覆った。
「えー、アイさんおめでとう!良かったねー!」
アカネは歓喜してアイを抱きしめる。
「やっぱりすごいなー!俺ももっとがんばらないと席がなくなっちゃいそうだ」
自虐を混ぜながらタツヤも笑う。
「皆さんが色々教えてくれたおかげです…。本当にありがとうございます」
まだ信じられないような表情をしているアイだが、喜びは確かに感じていた。
(私にも、人の心を動かすことができた…)
アイにとって大きな壁だったセールスライティングは、大きな変化を与え、成長につながった。
そんなアイをミツルは笑顔で祝福する。
「アイさん、おめでとう!今後も同じライターに依頼したいと言っていたので、お願いしてもいいですか?」
アイは大きく頷く。
「先輩、今日は食事会するしかないですね!」
アカネが目をキラキラさせながら言う。
「そうだな、皆の都合が大丈夫そうなら一緒にお祝いしよう」
今夜の食事会は賑やかになりそうだ。
お昼になると、アイとアカネは休憩室に向かった。
いつも通り他愛もない会話をするが、アカネにはどうしても気になることがあった。
以前アイが話した恋愛感情についてだ。
「アイさん、前に私に恋愛感情について聞いたことがあったよね?」
アイは静かに頷いた。
「アイさん、もしかして恋愛感情を持っているんじゃない?」
不意をついた言葉に、アイは思わず下を向く。
(やっぱり…。きっと相手は…)
アカネはアイの気持ちを察知し、あえて相手のことは尋ねなかった。
「その気持ちを伝えようと思ってる?」
アイは返答に困った。
「確かに恋愛感情と呼べるものは持っていると思います。でも、私はアンドロイド。誰かと付き合う前提で作られていません…」
アカネは、アイが自分の存在と気持ちの狭間で迷っていることを理解した。
「確かに前例はないかもね。私も聞いたことがない。でも、前例がなきゃダメかな?」
アイは顔を上げてアカネを見つめる。
「アイさん、自分の会社で過去に感情を持ったアンドロイドはいない、前例がないって言われたんだよね?でも、今のアイさんは私たちに欠かせない仲間になった。アイさんにとっても私たちにとっても初めてのことだよね?」
アイは頷く。
「だったらさ、今回もアイさんが初めての事例になってもいいんじゃない?アンドロイドと人間の恋愛だって、何十年もすれば当たり前になっているかもしれないし」
過去の事例やデータをもとに意思決定するアンドロイドにとって、それは考えもしないことだった。
「事例やデータも大切だけどさ、私たちにとって一番大切なのは気持ち。今何を感じてこれからどうしたいかだと思うな!」
アイは躊躇したが、アカネに質問をする。
「アカネさんは自分の気持ちに正直になっていますか?失礼かもしれませんが、私にはそう見えません…」
今度はアカネが目を丸くした。
アイにはミツルのことを何も話していなかったからだ。
「アイさん…鋭いね…」
頭を掻きながらアカネが答える。
「そう!人間は矛盾する生き物なのよ!気持ちは大切でも、その通りに行動できないこともあるの」
アイは首を傾げた。
「難しいですね、人間を理解するのは…」
これもアイの素直な気持ちだ。
「私は私が思った通りに行動する。だから、アイさんも自分の気持ちに従って行動するのが一番だと思うよ!」
アイは頷き、アカネとの世間話を楽しんだ。
仕事が終わると、一同は食事会の会場へと向かった。
ビールとおつまみを注文し、乾杯の時間が来た。
「アイさん、本当によくがんばりましたね。今日は皆でアイさんの成果を祝いましょう。乾杯!」
ジョッキの音が響き、それぞれ一気にビールを流し込む。
「改めて、皆さんサポートしていただきありがとうございました。今回の仕事を通じて、より感情についても学べました」
アイは深く頭を下げ、皆に感謝を伝える。
「いいよいいよ、仲間なんだから一緒に試行錯誤するのは当然だって」
タツヤの思わぬ発言に、一同の視線が集まる。
「ほら、早く食べないと揚げ物冷めちゃうよ!」
顔を赤くしたタツヤを見て、皆が笑う。
タツヤも大きく成長した1人だ。
これまではあまりコミュニケーションをとりたがらなかったが、今は会話をする機会も増え、仕事の連携もスムーズにできている。
そんなタツヤを見て、ミツルは微笑んでいた。
(本当、皆変わったよな。変わってないのは俺だけか…)
そんなことを考えながらビールを流し込む。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、現地で解散した。
アカネは前回と同じようにミツルと駅まで歩いていたが、公園を見つけてミツルに少し休みたいと伝える。
「何か飲み物買ってこようか?」
ベンチに座ったアカネを心配したミツルが尋ねる。
「大丈夫です。ちょっと飲みすぎちゃったかな」
いつもの明るいアカネとは違う様子に戸惑いながら、ミツルも隣に座る。
「今日は月が綺麗ですね。久しぶりに満月を見た気がします」
ミツルもアカネにつられて空を見上げる。
「本当だ。俺もいろいろと忙しくて夜空なんて久しく見てないかもしれないな」
ミツルの横顔を見ながら、アカネが尋ねる。
「先輩、先輩にとって大切なものって何ですか?」
ミツルは驚いたようにアカネの方を向く。
そして、アカネの表情を見て真剣に尋ねていると察した。
「うーん、仕事と一緒に働く皆かな」
「それだけ…?」
アカネが首を傾げながら質問する。
「どうした、そんなに酔ってるのか?」
ミツルの心配をよそに、アカネはゆっくりと語り出す。
「私が入社してから、先輩はずっとフォローしてくれましたよね。もちろん、仕事だからっていうのはわかっています。でも、私はそんな誰にでも優しい先輩が好き」
アカネは自分の気持ちをそのままミツルに伝えた。
「今は返事はいりません。気持ちが決まったら教えてください」
そう言ってアカネはその場を後にした。
まさかの展開に、ミツルはその場から動けなかった。
翌日、アカネは何事もなかったかのようにミツルやアイと話をしながら仕事を進めていた。
ミツルもいつも通り仕事をこなす。
仕事が終わると、いつものようにタツヤが先にオフィスを出る。
「お先に失礼しますー」
アカネもその後を追うように帰宅した。
ミツルが仕事を続けていると、アイが帰宅していないことに気がついた。
「あれ、アイさんは帰宅しないんですか?」
特に急ぎの仕事を振った覚えがなかったので、ミツルは疑問に思った。
「はい、もう少しだけやりたいことがあって…」
「何かあれば手伝うので、声をかけてくださいね」
そう言ってミツルは自分の仕事を進める。
1時間ほどしてミツルの仕事は終わり、再びアイに声をかけた。
「俺の方は終わったんですが、アイさんはどうですか?」
「私ももう終わりました。あ、ちょっとお話いいですか…?」
「はい、ここでもいいですか?休憩室のほうがいいですか?」
「ここで大丈夫です…」
「あの…ミツルさん今の私ってどう映っていますか?」
予想していなかったアイからの抽象的な問いに、ミツルは少しの間考えた。
「そうですね…。とても信頼できるなと感じています。仕事は丁寧だし、感情を理解できるようになって周囲とのコミュニケーションも良好になっていますからね」
「そうですか…」
恋愛感情を初めて抱いたアイにとって、どう話を進めたらいいのかわからず沈黙が流れる。
「何かあったんですか?その、心配ごととか…」
いつもと様子の違うアイを見て、ミツルは何かあったのではと考えた。
「ミツルさんの言う通り、私は感情を理解し、感情と呼べるものも抱くようになってきました。誰かを想う時に温かさを感じたり、時には胸が苦しくなったり…。ごめんなさい…。私、ミツルさんを好きになってしまいました…。こんなアンドロイドに言われても困るのは承知しています」
そう言ってアイは下を向いてしまう。
今まで感じたことのない胸のドキドキで、回路がショートしてしまうのではと心配していた。
「そうだったんですね…。俺はそんなに優れた人間じゃないのに…ありがとうございます」
ミツルは、アイの言葉から人間とアンドロイドの関係性について葛藤していたと考えた。
「返事には少しだけ時間をください。じっくり考えてみたいので」
ミツルの返事に、アイは頷く。
家に帰ったミツルはシャワーも浴びずにベッドに倒れ込んだ。
まさかアカネとアイから想いを告げられるなんて想像もしていなかったからだ。
(俺も変わらないといけないな)
あまり恋愛が得意ではないミツルだったが、改めて2人の気持ちと向き合うことを決意した。
それから1週間、タカハシ企画ではいつも通り仕事をこなしていた。
アイとアカネはそれぞれの気持ちを伝えたことを知り、より関係が深まったように見える。
ミツルはじっくりと考え、1つの結論を出した。
ある日の夕方、帰ろうとするアカネにミツルが声をかける。
「アカネ、ちょっと頼みたいことがあるから残ってくれないか?」
「はーい、少しならいいですよ!」
アイはミツルが返事をするのかもと思い、静かにその場をあとにした。
「この前の返事なんだけど…」
アカネは何も言わずにミツルの言葉を待つ。
「すまない、アカネの気持ちには応えられない」
そう言ってミツルは頭を下げる。
「何となくそんな予感はしてましたけどね!でも、これで自分の気持ちはハッキリしましたか?そしたらちゃんと伝えてあげてくださいね!本当、仕事はできるのに恋愛は超がつくほど奥手なんだから…」
アカネはスッキリしたような声で言った。
悲しくないと言ったら嘘になるだろう。
でも、ずっとお世話になっていた人のことを想えば気持ちを伝えて良かったと納得できた。
「じゃ、お疲れ様でした!また明日!」
そう言ってアカネはオフィスを出ていく。
残されたミツルは何もかも見透かされていたような気持ちになり、無意識に頭を搔いていた。
そして、その場で電話をかける。
「もしもし、アイさん?今少し話せますか?」
電話の相手はアイだった。
「少し会ってお話をしたいのですが…。え?まだ近くにいるんですか?」
何となくアカネとミツルが気になって、アイは真っすぐ帰れなかったのだ。
近くの公園にあるベンチに座っていたアイのもとに、ミツルが走ってやってきた。
「はぁはぁ…すいませんお待たせしちゃって…」
普段走ることのないミツルは息を切らしながらやってきた。
「そんなに慌てなくてもよかったのに…」
アイはミツルの姿を見て心配になった。
ミツルもアイの隣に座り、ゆっくりと息を整える。
「何年かぶりに全力で走りました」
そう言ってミツルが笑う。
アイは走っても疲れることがないので、その様子をじっと観察していた。
外見をどれだけ似せても、自分はやはりアンドロイドなのだと考えながら。
「この前の返事なんですが…」
ミツルが話を切り出す。
「俺は人間で、アイさんのことをすべて理解しているとは思っていません。アイさんはこれからも変わっていくでしょう」
その言葉を聞いて、アイは俯く。
「でも、そんなアイさんをこれからも見守りたい、できることがあればサポートしたいと考えています」
まさかの言葉に、アイは顔を上げる。
「俺でよければ、これからもよろしくお願いいたします」
それがミツルの答えだ。
「でも…。私はアンドロイドですよ?ミツルさんと一緒に年齢を刻むことはできない…」
嬉しい反面、アイは現実とも向き合っていた。
「確かに、アイさんは年を取らないし、俺はだんだん年老いていくでしょう。人間とアンドロイドの関係性も大きく超えることだと思います」
「でも、人間は理屈だけでは生きていません。今の自分がそうしたいから決めたまでです。それに、今は珍しくても何年、何十年経てば当たり前のことになるかもしれない」
その時、アイはアカネの言葉を思い出した。
(事例がないなら作ればいい…)
こんな時にどうしたらいいかわからないアイは、ミツルを見つめた。
「…よろしくお願いいたします」
それがアイの精一杯の返事だった。
アイとミツルに限らず、人間とアンドロイドの関係はこれからもどんどん変化していくだろう。
今は主従関係が当たり前でも、人間とアンドロイドの関係性も無数にできる日も遠くないかもしれない。
それが、人間とアンドロイドの真の共存になるだろう。
ー完ー