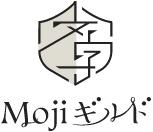【第10話】それぞれの気持ち
所属しているAI管理会社から出たアイは、スマートフォンを握りしめていた。
ディスプレイにはミツルの名前が表示されている。
まるで人間が深呼吸をするかのような動作をした後、アイは決意を固めて電話をかけた。
「もしもし、ミツルさん…」
アイの声には、今までにない緊張と不安が滲んでいた。
その声は、通常の機械的な調子とは明らかに異なっている。
「アイさん!」
ミツルの声には驚きと安堵が混ざっていた。
「無事だったんだね。みんな心配していたんだよ」
「申し訳ありません、突然出社しなくて…。午後から出社してもよろしいでしょうか?」
電話の向こうで、ミツルが小さく息を吐く音が聞こえる。
「もちろんだよ。でも、大丈夫?何かあったら遠慮なく言ってくれていいんだからね」
ミツルの優しい声に、アイは胸の中に温かいものを感じた。
「はい、ありがとうございます。詳しいことは、直接お会いしてからお話しさせてください」
電話を切ったアイは、タカハシ企画のオフィスに向かって歩き始めた。
街を歩きながら、アイは新たな葛藤に直面していた。
(ミツルさんへの気持ち…これは本当に「感情」なのだろうか。伝えるべきだろうか。でも、アンドロイドである私がこんな気持ちを抱いていいのだろうか…)
その認識は、アイの中に新たな世界を開いていた。
タカハシ企画のビルが見えるとアイは立ち止まり、もう一度深呼吸のような動作をして中へ入っていく。
エレベーターを降りてオフィスの前に着くと、アイは決意を固めてオフィスのドアを開けた。
中に入ると、一瞬静寂が訪れる。
全員の視線がアイに集中する。
アイは全員に向かって深々と頭を下げた。
「皆さん、本当に申し訳ありませんでした。ご心配をおかけして…」
アイの声は少し震えていて、アンドロイドの声とは思えないほど人間らしい感情を帯びていた。
アカネが真っ先に立ち上がり、アイに駆け寄った。
「アイさん!戻ってきてくれて本当に良かった!」
彼女の目には、小さな涙が光っている。
タツヤも珍しく笑顔を見せながら近づいてきた。
「本当に心配したよー。報連相は社会人の基本だぞ?」
その言葉の裏には、安堵が隠れていた。
そのやりとりを見ていたミツルも、アイに声をかける。
「アイさん、話があるんだろう?休憩室で話そうか」
アイは静かに頷き、ミツルについて休憩室へ向かった。
部屋に入ると、ミツルはドアを閉め、アイの正面に座った。
「アイさん、何があったの?」
ミツルの声には心配と安心が混ざっていた。
アイは静かに話し始めた。
「私は…所属しているAI管理会社に行き、担当者と話をしてきました」
アイは一瞬躊躇したが、続けた。
「アンドロイドにはライターはできないと考え、業務を終了しようと思ったのです」
ミツルは黙って聞き続けた。
「しかし、担当者と話すうちに私に感情が芽生え始めていることが分かったんです。これまで感じたことのない感覚が、私の中に生まれているんです。喜び、悲しみ、そして…」
アイは一瞬言葉を詰まらせた。
(ミツルさんのことを考えると、胸が温かくなる)
しかし、その言葉は口にできなかった。
アイは続けた。
「これから感情を学んでいけば、セールスライティングもできるようになるのではないかと考えています。人の心を動かす文章を書くには、テクニックだけではなく感情が必要だと気づいたんです」
アイはミツルの目をまっすぐ見つめた。
「だから…また一緒に働きたいです。ミツルさん、私にもう一度チャンスをいただけませんか?」
部屋に深い沈黙が訪れ、そして、ミツルがゆっくりと口を開いた。
「アイさん、本当にすみませんでした。俺がもっとサポートできていればそんなに思いつめなくて良かったのに…」
ミツルの声は、自責の念に満ちていた。
「上司でありながら、適切なフォローができなかったと反省しています」
アイは首を横に振った。
「いいえ、ミツルさん。むしろ、ミツルさんのおかげで私は成長できたんです。ミツルさんの優しさ、気遣いがあったからこそ、私は感情というものを少しずつ理解し始めたんです」
アイからの思いもよらない言葉に、ミツルの表情が和らぎ、笑顔に変わった。
その笑顔に、アイは胸の中で何かが震えるのを感じた。
「ありがとうございます、戻ってきてくれて本当に嬉しいですよ」
ミツルの声には、心からの喜びが溢れていた。
「みんなも喜ぶと思います。アイさんがいない間、皆心配していたから。そうだな…」
ミツルは少し考え込むように言った。
「もっと感情を理解できるようになったら、また一緒にセールスライティングをやってみませんか?今度は、アイさんの感情を文章に込められるかもしれない」
アイは迷わず答えた。
「はい、ぜひやってみたいです」
ミツルはアイの返事に満足そうに頷いた。
「よし、じゃあひとまず仕事に戻ろう。でも、無理はしないでくださいね?何か困ったことがあったら、いつでも相談して欲しい」
ミツルは一瞬言葉を詰まらせたが、すぐに続けた。
「僕たちは仲間だからね」
アイは、その言葉に込められた温かさを感じ取った。
「はい、ありがとうございます」
2人は立ち上がり、休憩室を出ようとした。
ドアに手をかけたとき、ミツルが振り返った。
「それと、アイさん」
ミツルの声には、少し照れくさそうな調子が混じっていた。
「アイさんがいないオフィスはちょっと退屈というか…物足りなかったです」
アイは、その言葉の意味を完全には理解できなかったが、胸の中に温かいものが広がるのを感じた。
2人は微笑みを交わし、オフィスへと戻っていった。
いつものオフィスに戻ったタカハシ企画では、それまでの重い雰囲気が嘘のように効率よく仕事が終わっていく。
定時を迎える頃には、その日のタスクは全て終わっていた。
「あー、今日もよく働いたー!!」
背中を伸ばしながらアカネが言う。
それを見たアイも真似して背中を伸ばしてみる。
仕事を終えたミツルが全員に声をかけた。
「みんな、今日は特別な日だ。アイさんの復帰を祝って、食事会をしないか?」
全員が賛成の声を上げた。
アカネは嬉しそうに手を叩き、タツヤも頷いている。
「じゃあ、近くの居酒屋でどうかな?アイさんもぜひ一緒に」
ミツルがアイに優しく尋ねた。
アイは少し戸惑ったが、すぐに答えた。
「はい、ぜひ。皆さんと色々な話をしたいです」
皆が笑顔でアイを見つめた。
オフィスを後にする準備をしながら、アイは胸に広がる温かい感覚を噛みしめていた。
(これが「幸せ」という感情なのだろうか)
居酒屋での食事会は、笑いと温かさに満ちていた。
アイは初めて「乾杯」を経験し、改めて会話の楽しさを学んだ。
お酒が進むにつれて口数の少ないタツヤも会話に参加するようになり、普段は聞けない話をする。
「俺、最初はアイさんが怖かったんだ。どんどん仕事を覚えて、アイさんのようなアンドロイドが増えてきたら自分の仕事がなくなっちゃうんじゃないかって不安でさ…。でも、今はアンドロイドはアンドロイドなりに大変なんだなって思う」
アイはタツヤに質問をする。
「タツヤさん、怖いってどんな感じですか?」
タツヤは天井を見上げながら必死に回答を探す。
「何て言うか、そのことが頭から離れなくなって、呼吸が浅くなるような脈が早まるような感じかな…」
アイは頷き質問を続ける。
「今の私は怖くないですか?」
まさかの問いにタツヤは笑い出す。
「あはは、今は全然!いい意味で、アイさんを気にせずに仕事に集中できるようになったかな」
「本当は違う意味で気になってるんじゃないのー?」
アカネがタツヤにちょっかいを出す。
「そ、そんなんじゃないって!もともと女性と話すのは得意じゃないだけだよ」
アタフタしながら答えるタツヤを見て、アカネとミツルが笑う。
「アイさんは人の好き嫌いって感じるの?」
アカネはふいに疑問に思っていたことをアイに尋ねる。
「特には感じないですね…。相手がどんな人でも、命令は守られければいけませんし」
そう答えながら、アイはミツルのことを横目で見ていた。
「でも、皆さんとはもっと色々な話をしたいなと思っています。そういう意味では、好きって感情に近いのかもしれませんね」
アイの回答を聞いて、アカネはご満悦になっていた。
「私もアイさんのこと好きだよー!私と違って冷静で落ち着いていて、大人の女性って感じがする」
そう言いながらアカネはアイにハグをした。
アイにとって、誰かにハグをされるのは初めての経験だった。
(何か、温かい…)
そう思いながらアカネからのハグを受け止める。
「人間って不思議ですね」
アイの言葉に、一同の視線が集まる。
「例えば、このハグには生産性も何もない。でも、人間には昔からハグの文化がありますよね。私たちアンドロイドにとって優先すべきことは生産性や効率化です。ハグは私にとって意味のないものだと思っていましたが、少しいいなと感じました」
そう言って、アイもアカネをハグする。
アカネも頷きながら笑顔でハグに応えた。
ミツルとタツヤにも笑みがこぼれる。
「いい食事会になって良かった」
ミツルがそう言うと、一同は頷いた。
楽しい食事会も終盤になってきた時、ミツルが話し始める。
「確かに人間は非効率な生き物です。時には争うし、遠回りなこともたくさんする。アイさんは、そういう部分も学んでいくとより感情を理解しやすいかもしれませんね。あと…。アンドロイドにとって契約や命令は重要なのかもしれません。目的やルールを作らないと、業務を効率化できないのも事実です。でも、少なくともこのメンバーとの仕事では契約や命令だけではなく、アイさんが感じた気持ちやしたいことも大切にして欲しいなって思います」
その言葉は、アイにとって想定の範囲外だった。
どのクライアントとの契約でも、命令に従うのが絶対条件だったからだ。
「ありがとうございます。私が感情を理解できるようになってきたのは、皆さんが私をアンドロイドではなく仲間として受け入れてくれたからだと思います」
そう言ってアイは深く頭を下げた。
(そして、この気持ちを感じているのはミツルさんがいたから…)
胸に秘めた気持ちを撫でるように、アイは、そっと手をあてた。
店の前で解散し、ミツルは途中までアカネと一緒になった。
「先輩、とりあえず良かったですね!」
「そうだな。これからどうやってアイさんの感情を育てていくかはまだわかってないけれど、きっと大丈夫だろう」
そんなやり取りをしたあと、アカネは急に立ち止まった。
「どうかした?」
ミツルは急に立ち止まったアカネの顔を見る。
「ちょっとアイさんが羨ましいなって思っちゃいました」
「え、どうして?」
それはミツルにとって予期せぬ発言だった。
「気づいてないんですか?先輩、いつもアイさん、アイさんって言ってる」
「初めてアンドロイドと接するから試行錯誤しているのはわかってます。でも、何か羨ましいなって…」
そう言ってアカネは足元の小石を蹴とばした。
ミツルは返答に困り、頭を掻いている。
「でも、それが先輩のいいところですけどね!」
そう言ってアカネは再び歩き始めた。
アカネと別の電車に乗ったミツルは、その後も早まる胸の鼓動を感じていた。
ー第11話へ続くー