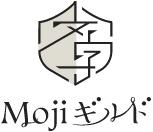【第2話】アンドロイドのくせに
「今日の納期はコレとコレか…予定組んでおかないとな」
オフィスに一番先に出社するのは、いつもディレクターのミツルだ。
その日の予定を確認し、皆が出社するまでに指示をまとめる。
静まり返ったオフィスで朝の仕事を済ませ、ミツルはコーヒーを注いだ。
朝のこの時間はミツルにとって特別だ。
(今日から本格的にアイさんも仕事に加わる。なるべくムダのないように進行していかないとな)
ミツルにとっても、アンドロイドと仕事をするのは初めての経験だ。
2040年の東京では、業種によってはアンドロイドと仕事をするのは珍しくない。
しかし、クリエイティブな現場でアンドロイドを雇用するのは、まだ例が少ない。
慎重派なミツルだからこそ、色々考えを巡らさずにはいられなかった。
「先輩、おはようございます!」
その時、ドアが開くと同時に元気の良い声がした。
いつも明るいアカネだ。
「おはよう、今日も元気いっぱいだな」
「もちろんですよ、私から元気をとったら何が残るんですか!」
そう言ってアカネは明るく笑い飛ばした。
「おはようございます」
アンドロイドのアイもドアを開けて挨拶をする。
「アイさん、おはようございます。今日からがんばりましょうね」
「アイさーん、おはよう!よろしくね!」
ミツルが微笑みながらアイに言うと、アカネも笑顔でアイに挨拶した。
「はい、こちらこそよろしくお願いします」
そんなやり取りをしていると、後ろからまた別の声がする。
「おはようございます」
タツヤだ。タツヤはいつも最後に出社してくる。
皆と挨拶を交わすと、そのままタツヤはデスクに移動した。
タツヤは人と関わるのがあまり得意ではない。
だからこそ、黙々と仕事ができるWebライターの道を選んだ。
「よし、そろそろ仕事を始めよう」
ミツルの声とともに、各自自分のデスクへと移動する。
「アカネ、いつも担当しているA社の追加案件頼めるか?」
「いいですよー!入稿までやっちゃいますね!」
ミツルは先にアカネに指示を出し、タツヤの元に向かった。
「タツヤ、この前の記事なんだけど、修正が入ったんだ」
「え、どこですか」
「製品の説明なんだけど、クライアントから具体的な内容にして欲しいって資料が届いた」
「わかりました。じゃ、それからやりますね」
「うん、よろしくな」
タツヤは資料を受け取り目を通した。
(だったら最初からそう言ってくれればいいのに…)
そんなことを考えつつ資料を読み終え、修正を始める。
「アイさんは、この案件のリサーチを進めてくれますか?」
「はい、わかりました」
資料に目を通し、アイもリサーチを開始する。
(ふん、アンドロイドのくせに…)
タツヤは横目でアイを見ながらそう考えていた。
あまり仕事熱心ではないタツヤは、仕事量が少なくなることは嬉しかった。
しかし、アンドロイドと一緒に働くことには否定的な考えを持っている。
(俺の仕事はアンドロイドにもできることなのか。だとしたら、俺はどうやってこの先働いていけばいいんだよ)
タツヤはプライドだけは人一倍高い。だからこそ、アンドロイドと同じ仕事をしたくないと考えていた。
もちろん、タツヤのその気持ちはオフィスにいる誰もまだ知らない。
「ミツルさん、リサーチは終わりました。ドキュメントにまとめてあります」
アイがミツルに伝えると、ミツルはドキュメントを確認した。
「アイさんありがとうございます。うん、問題ないですね。このまま記事化してくれますか?」
ミツルの言葉に、アイは頷く。
「わかりました。すぐに着手します」
そしてアイは再びパソコンに向かった。
「ミツルさん、俺ちょっと一服してきますね」
タツヤは席を立つとミツルにそう言った。
「いいよ、細かい指示が多いからタツヤも疲れただろ」
その言葉を聞きながらタツヤは屋上へと向かった。
(ミツルさんは本当に怒らないよな。俺みたいな奴の話もちゃんと聞いてくれるし)
学生時代や過去の職場では上手く周囲と打ち解けられず、タツヤは孤立することが多かった。
その経験から、周囲を信頼したり心を開いたりすることが苦手になってしまった。
そんなタツヤでも、ミツルの人柄だけは認めていた。
未経験でタカハシ企画にきたタツヤに、ミツルは1から丁寧に仕事を教えてくれたのだ。
タツヤの性格をわかってか、必要以上に深入りせず、でも評価し続けてくれている。
(ミツルさんはあのアンドロイドと一緒に働くこと、どう思っているんだろう)
タバコを消してオフィスに戻りながら、タツヤは心でそう呟いていた。
タツヤがデスクに戻ると、ちょうど1本の電話が入った。
「はい、タカハシ企画です!はい、少々お待ちください」
「先輩、この前納品したB社の担当者からお電話です。何か機嫌悪そうですけど…」
そう聞くとミツルが電話を代わった。
「お電話代わりました。お世話になっております。はい…」
しばらくミツルは話を聞いていたが、事態は深刻そうだ。
「それは大変申し訳ありません。はい、至急対応します」
電話を切ると、ミツルは考え込んだ。
「先輩、大丈夫ですか…?」
アカネが心配になって声をかける。
「あぁ、ちょっとクレームが入っただけだ。すぐに対応すれば問題ない」
「タツヤ、ちょっと来てくれるか?」
ミツルがそう言うと、タツヤは不安そうな顔でミツルのデスクに向かった。
「この前書いてくれた記事なんだけど、統計データが間違ってるらしいんだ。どのデータを使った?」
ミツルの問いにタツヤはもじもじしながら答える。
「あれはその、検索エンジンの上位に出てきたサイトにあったデータを使いました」
数字などのデータを使用する時は、必ず関係省庁や企業のデータを使うという決まりがあったのだ。
「やっぱりそうか。忙しいのはわかるんだけど、それはやっちゃダメだよ」
ミツルが静かに伝えると、タツヤは慌てて言った。
「すいません、すぐに修正します…」
タツヤの申し出をミツルはやんわりと断った。
「いや、タツヤは今の仕事を続けてくれ。アイさん、ちょっといい?」
そうしてミツルはアイを呼んだ。
「至急このデータを集めて修正してくれませんか?」
ミツルの依頼にアイは頷く。
「わかりました。すぐに着手します」
アイがそう言って席に戻ろうとした時だった。
「いいよ、俺のミスなんだから自分で対処できる。アンドロイドのくせに邪魔するな!」
タツヤはアイに向かって言い放った。
アイがタツヤの方を振り向くと、タツヤは続けて言った。
「俺はお前なんかより経験もあるし、いい記事だって作れる!だから俺の仕事の邪魔をするな!」
タツヤの声が静かなオフィスに響いた。
それを聞いたアイは何も言わず、ミツルに視線を向ける。
「タツヤ、ちょっと屋上に行こうか。アイさん、その仕事は進めてください」
ミツルはそう言ってタツヤと屋上へ向かった。
屋上に着くと、ミツルはタツヤに問いかける。
「タツヤ、どうしたんだ?いつものお前らしくないじゃないか」
ミツルに怒っている様子はなく、むしろタツヤを心配していた。
「ミツルさん、すいません。どうしてもアンドロイドと仕事するのが嫌で…」
タツヤはうつむきながら言った。
「嫌?どうして?」
ミツルは意外な返答に驚きながら返答する。
「だって、俺たちのやっている仕事はクリエイティブじゃないですか!アンドロイドができるようになったら、俺必要なくなるし…」
タツヤは自分の存在価値がなくなることを恐れていた。
やっと働きやすい職場に出会ったという気持ちから、アイの存在を脅威と感じていたのだ。
「そういうことか…俺の考えではアイさんもタツヤも、どちらも必要なんだけどな」
ミツルからの答えに、タツヤは首を横に振った。
「だって、俺ミスも多いし、そんなに仕事熱心ってわけでもないし…」
「アイツなら言われたことを正確にこなすでしょ?だったら、俺なんていなくても…」
タツヤがそこまで言った時、ミツルはタツヤの肩に手を置いた。
「確かにタツヤはミスするし、残業の時に嫌な顔するけどな!」
「でも、未経験から必死になってがんばってきただろ?すぐに辞めちゃう人が多いなか、それは凄いことだと思ってるよ?」
ミツルの言葉に、タツヤが顔を上げる。
「タツヤ、アイさんはお前の敵じゃない。同じタカハシ企画の仲間だ。俺にとってはどちらがいいとか関係ないよ」
ミツルが笑いながら伝えると、タツヤはまたうなだれる。
「ミツルさん、本当にすいません。俺とんでもないこと言っちゃった…」
改めて落ち込むタツヤに、ミツルは背を向けながら言った。
「一言アイさんにごめんって言えばいいさ。俺は先に戻るぞ」
1人取り残されたタツヤは、気持ちを落ち着かせるためにタバコに火をつけた。
(俺、自分に自信がなかっただけなんだな。何年もライターをしてきた自分の存在価値が無くなるかもしれないって考えてた)
何より、タツヤにとってはミツルから必要だと言われたことが嬉しかった。
これからもミツルと一緒に働くためには、アイとも一緒に働いていかなくてはいけない。
(俺は俺のやり方でアンドロイドに負けない記事を作る)
いい意味で、タツヤはアイを意識しようとしていた。
タバコを消してオフィスに戻ったタツヤは、まっすぐアイのデスクへ向かう。
「あの…さっきはすいません…」
小さい声でタツヤが言うと、アイはタツヤの方を向いた。
「大丈夫です、仕事を続けましょう?」
そう言ってアイは再び仕事を再開する。
タツヤもデスクに戻って仕事を再開した。
クレームのあった案件はアイが対応し、無事にクライアントからも承諾を得られた。
「んー、今日も終わったな!タツヤ、たまには夕飯一緒にどうだ?」
ミツルがタツヤに言う。
「はい、俺もう腹ペコで…早く行きましょう!」
タツヤは珍しく反応し、パソコンを終了させた。
「じゃ、私たちも帰りますね!」
アカネとアイも片付けを済ませ、席を立つ。
「わかった、2人ともお疲れ様ね」
「お疲れ様でした!」
アカネとアイはそう言って先にオフィスを出た。
「よし、俺たちも行こう!タツヤ、今日は何が食べたい?」
ミツルの問いにタツヤは目を輝かせていた。
ー第3話へ続くー