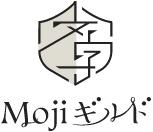1【基本のキ!】取材とはどんなもの?
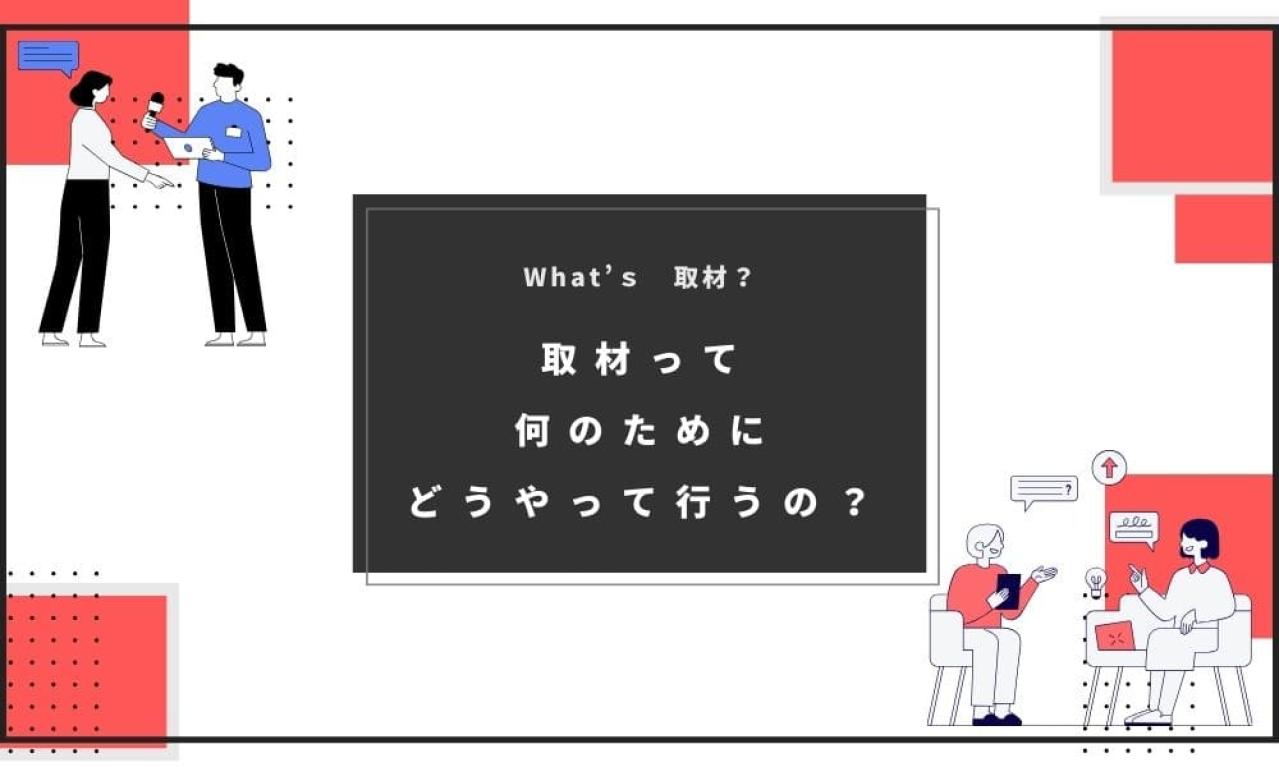
取材とは単語としては聞き慣れていますが、実際はどんなものなのでしょうか。ここでは、そもそも取材とは何なのかを解説します。
取材は何のために行うのか
取材とは、一言でいえば情報収集の手段です。取材から得られた情報には、次のような強みがあります。
- 情報の出所がハッキリわかる
- 取材で得た情報ということ自体が説得力を生む
- ライター自身の体感・感想を情報として加えられる
文章を書く際、根拠となる情報の有無は、文章の説得力を左右する極めて大切な要素です。Web検索では得られにくい情報を使いたい場合、確かな出所から情報を得るためには取材が必要となります。
しかし取材のように、現地や関係者から情報を得る行為は、本来とても労力が必要なものです。読者も「知りたいけれど、自分の時間・労力をかけることは億劫」だと思っています。だからこそ取材からは、求められる情報が生まれるのです。
五感をフルに使って、取材ならではの活き活きとした情報収集にぜひチャレンジしてみてください。
取材の種類
一口に取材といっても、方法や手段にはバリエーションがあります。それぞれの内容については当サイトの過去コラムで解説していますので、本記事ではざっくりと触れることとします。
以下のようにこのようにさまざまな手法がありますが、どのような方法を選ぶかは、集めたい情報の程度や、インタビュアー(質問者)とインタビュイー(質問される側)の関係性や距離感、掲載媒体のテイストなどで選択します。
| 取材対象 | 個人 | 取材対象にまつわる情報を、会話や体験を通して収集することが取材である。 |
|---|
| 完成記事の型式 | Q&A形式 | ・インタビュアーの質問と、インタビュイーの答えが交互に繰り返される会話調のスタイル。 |
|---|
| 取材の手段 | 訪問 | 取材対象との物理的な距離感や、時間の制約などで適切な方法を選択する。 |
|---|
それぞれのより詳しい解説を知りたい場合は、こちらを参考にしてください。
取材記事ができあがるまでの流れとは
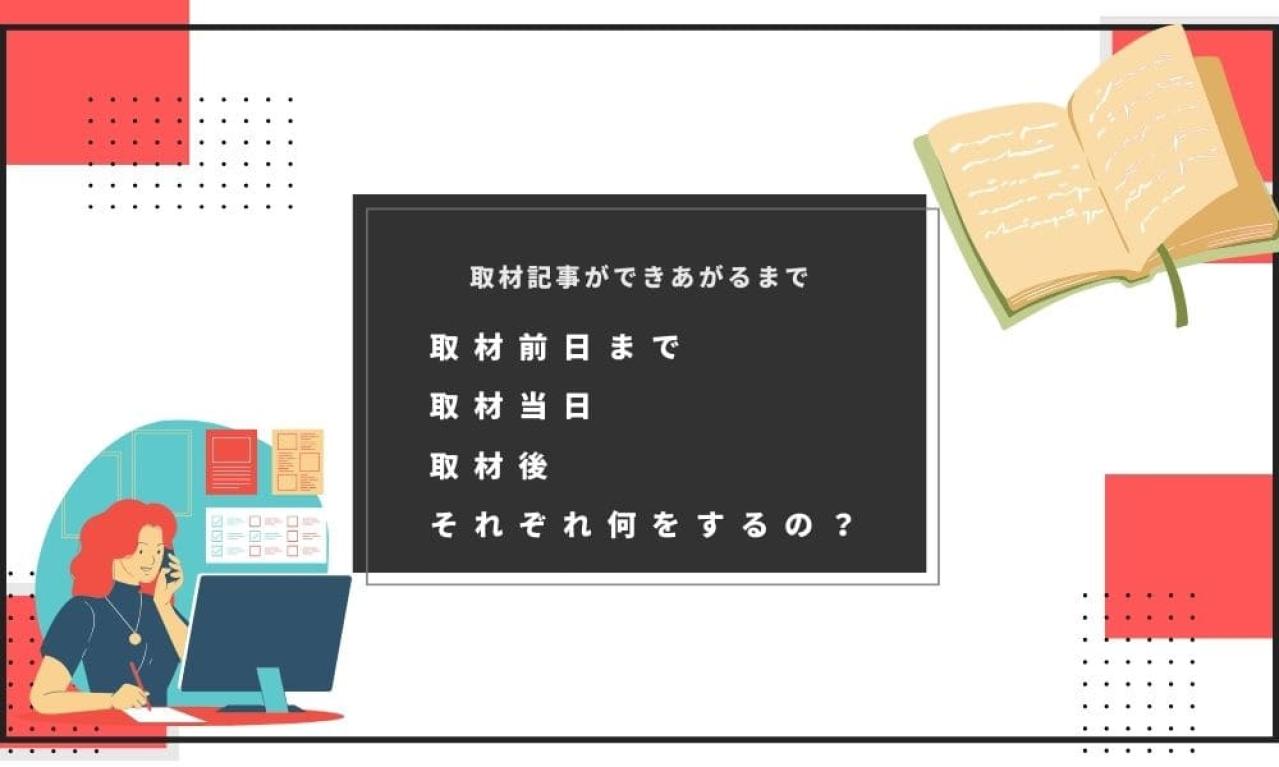
ライターが受ける取材依頼は、多くのケースで取材記事の執筆までが依頼内容に含まれます。それでは、取材記事はどのようにして仕上げていくのでしょうか。ここでは取材記事制作の大まかな流れを、「取材前日まで」「取材当日」「取材後」に分けて解説します。
取材前日まで
取材記事制作の依頼を受けたら、まずは取材先と連絡を取り、取材の可否と取材日時を確定させましょう。取材オファーを出したのが編集プロダクションやポータルサイト運営者である場合、担当者が取材先とライターとの間に立ち、アポイントを調整してくれるケースもあります。
取材日が確定したなら、ライターは取材前日までに取材の準備を行います。具体的には、以下のような準備が必要です。
- (オフラインの場合)取材場所までのアクセス確認
- (オンラインの場合)ミーティングツールの選定、ミーティングルームURLの発行
- 録音・録画機器やカメラの準備
- 取材対象に関する情報のリサーチ(企業のWebページ、過去の取材記事など)
- 取材当日の質問事項の作成、取材先への共
取材は、基本的にはやり直しがききません。そのため、取材前の計画づくりがとても重要になります。手順や方法などをしっかりと確認してから取材に臨みましょう。
取材当日
いよいよ取材当日です。あいさつを済ませ、録音・録画の許可を確かめてから、取材をスタートしましょう。
取材では、インタビュアーのかじ取りが重要です。インタビュイーには、次々と話が広がる方や、取材自体に苦手意識をもっている方もいます。決められた時間内に十分な情報を得られるよう、インタビュアーがうまく誘導してください。
一通り話し終えたなら取材は終了ですが、退室する前に「都合のつきやすい連絡先」を確認しておくとよいでしょう。というのも、取材後には次のようなことで取材対象者に連絡を取る機会があるからです。
- 情報の正誤を確認したいとき
- 公開前に原稿のチェックをお願いしたいとき
- 取材対象者に写真提供をお願いしたいとき
上記のときに、取材対象者へダイレクトに連絡できる連絡先があるかないかでは、その後のスムーズさが変わってきます。
そのほかの、取材前や取材当日のポイントについては、ぜひ以下のコラムも参考にしてください。
取材後(執筆~公開)
取材を終えたら、記事の執筆です。当日のメモ・録音・録画を確認しながら、記事を執筆します。途中でわからないことがあった場合は取材先に確認をしましょう。
そして取材記事ができあがったら、公開する前に必ず取材対象者への内容チェックをお願いします。情報の誤りや、取材でのニュアンスをうまくくみ取れていない部分がないか確認してもらい、OKをもらえたらいよいよ公開です。
記事が無事に公開となったなら、ぜひ取材先へ報告しましょう。取材を受けてもらったことへの感謝の言葉を添えるなど、お互いが気持ちよい関係を続けられる心配りができるといいですね。
私が取材で大切にしているポイント
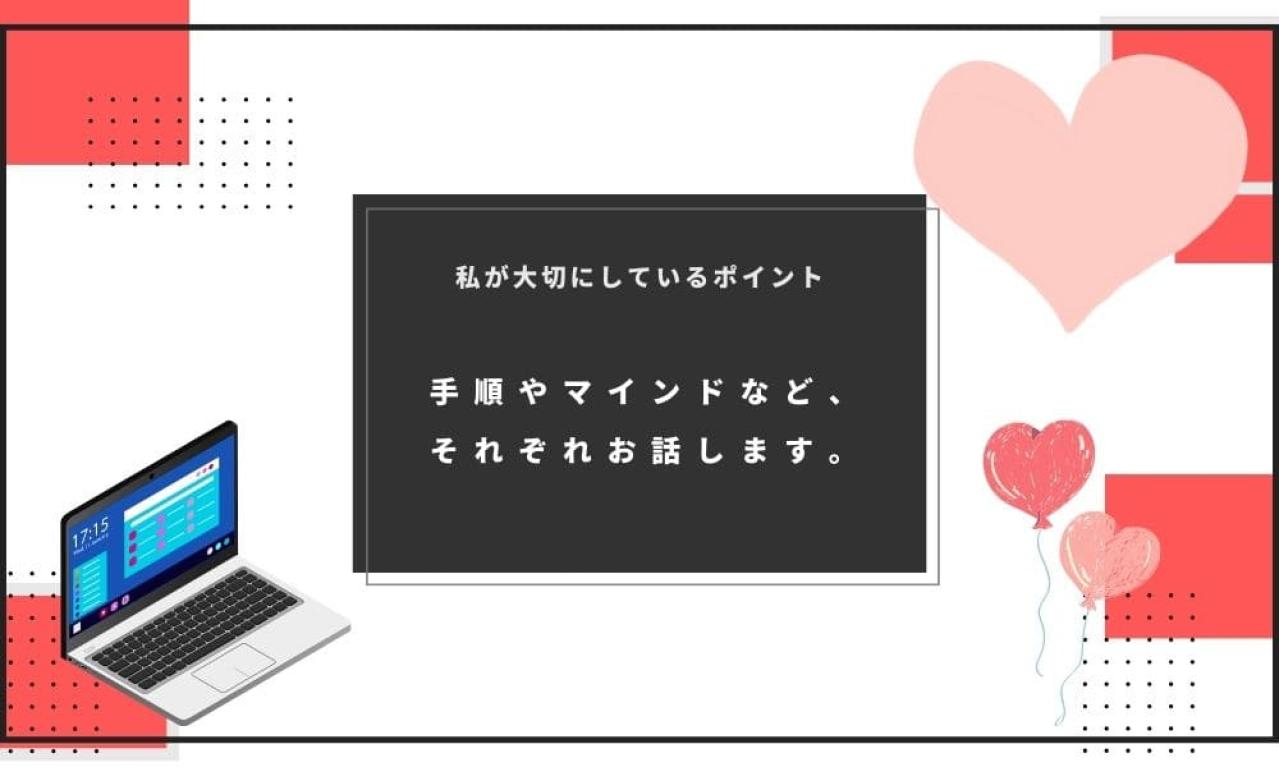
取材ライターとして活動するうえで、私なりに大切にしているポイントをお伝えします。すべてが正解だとは思いませんが、何か参考になるものがあれば嬉しいです。
取材前に記事の構想を十分に練っておく
取材記事の執筆というと、取材後におもしろかった内容をピックアップしてゼロから構成を練り、記事をつくる方もいるかもしれません。しかし私の場合は、取材の準備段階で、ある程度の記事の構成を考えておくように心がけています。
その理由は、質問の優先順位を考えるためです。取材は時間との闘いになります。重要度の高くない質問で話が広がりすぎると、終盤で時間に追われてしまうことも……。そのため、質問の重要度と、ざっくりとした時間配分を意識しながら進行することがとても大切です。
質問の重要度を事前に把握するために、必要となるのが構成案です。「誰に・どんな内容を届ける記事にしたいのか」を軸に完成記事のイメージを練り、想定される字数を目安にして質問の重要度を考えましょう。
しかし取材では、想定していなかったおもしろい話が出てくることも多々あります。その場合は、取材前の構成にとらわれすぎず、取材後に改めて構成を練り直せばOKです。
取材する人・される人の協力体制を築く
取材をスムーズに進めるための特効薬は、取材対象者と取材目的を共有することです。「誰に・何を伝えるためにこの取材をするのか」を、取材日より前に伝え、取材開始時にも再確認しましょう。すると取材される側も、質問の意図に合った答え方を考えながら話してくれます。
例えば、会社員さんへ「会社の良いところ」を質問する場合でも、それが商品PRのために聞いているのか、求人のために聞いているのかによっても、欲しい情報が微妙に変わってきますよね。「欲しい情報がピンポイントに返ってくる」のはライターにとってのメリットですが、質問に答える側にも「答えるべき情報のヒントとなり話しやすい」と感じるものです。
ぜひ取材の目的意識を揃え、取材対象者と二人三脚で取材を進めましょう。
全力で取材先の味方になろうとする
私が一番大切だと感じていることは「取材先の味方になろうとすること」です。
取材とは、取材される側にとって負担を少なからずかけてしまいます。取材のために時間をつくること、言葉の一語一句に気を配ること、自身の立場に合わせた振る舞いをすること。正直めちゃくちゃ大変ですよね。
それにも関わらず取材を受けてくれるのですから、ライターは取材を受けてくれる側に最大限に寄り添い、不安を取り除き、一番の味方となり、感謝をベースに行動する必要があるのではないでしょうか。間違っても「取材してあげる」なんて思い上がった態度をとるのはもってのほかです。
メディア・ライター・取材対象者は、互いに助け合うことで存在できています。互いを大切にすることで、すべての人が幸福になる発信の方法を互いに見つけていけたらいいですね。
取材は楽しい!レッツチャレンジ

以上、取材の基本知識やざっくりとした制作の流れ、私なりに大切にしているポイントなどをまとめました。
ライターさんのなかには、取材に興味はありつつも、「やり方がわからない」「失敗が怖い」などが理由で、及び腰になってしまっている人もいるかもしれません。しかし、取材を経験している身から言うと、取材はとても楽しいものです。取材対象と向き合い、掘り下げ、記事に落とし込む作業は、リサーチした情報をまとめる執筆とは違ったおもしろさがあります。
勇気が出たなら、レッツチャレンジ。あなたの取材体験が、素晴らしいものになることを願っています。
この記事を書いたライター

加橋もと春(motohal)
「誰か」と「読み手」をつなげる文章をつくる、ライティングという仕事にやりがいを感じています。人物取材や製品コピーなどのストーリー性・メッセージ性のある記事制作、FP等のマネー系資格を活かしたSEOライティングなどが得意です。現在はフ...