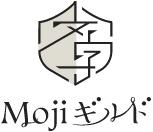完璧
私は鏡に映る自分の姿を見つめた。
シワのない陶器のような肌に薄くチークを重ね、桜色の唇をグロスで艶っぽく仕上げる。
「完璧」
小さく呟いた言葉に、わずかながら言葉代がかかる。でも、自分への称賛なら惜しくはない。
私は美容クリニックの受付として働きながら、給料はすべて美容に費やしてきた。
仕事中も、課金されてしまう同僚との会話はほとんどしない。
仕方なく会話しなければならないときは、テキストを使用するようにしている。
そんな私を見る目が冷ややかなのも、わかってはいる。
それでも他人との会話を極力避け、美しくあり続けたい。
(会話にお金を払うなら、シミの1つでも取ればいいのに)
『無駄遣い』という言葉が、頭をよぎる。
ただ、美しくありたい。
美しくなければ、幸せは訪れない。
ルッキズム
美意識に目覚めたのは、高校生の頃だった。
「美香、今日はなんだか肌の調子が良くないんじゃない?」
母はそう言って、手作りのスムージーを置いた。
わたしの母は、美しく完璧な女性だった。
商社勤めの父に溺愛され「君は本当に美しい」と言われるたびに、頬を染める姿は20代でも十分に通用するだろう。
人から愛されるというのは、母のようになることだと、幼い頃から思っていた。
実際に母は、私の見た目にも、とても厳しかった。
思春期に入ってニキビが目立つようになると、毎日肌にいいスムージーが日替わりで出され、添加物が入った食べ物が家から消えた。
スタイルが悪くならないようにと、下着や靴を選ぶのも、すべて母だった。
早く肌を綺麗にしなければ。体型がくずれないようにしなければ。
いつしか自分の見た目にしか、興味を持てなくなっていた。
(私もいつか、母のように、誰かに愛されたい)
それが私の夢だった。
そんな私の日常に、変化が訪れたのは春のことだった。
クリニックに新しい医師が赴任してきた。藤堂真也、38歳。
端正な顔立ちと優しい物腰で、たちまち女性患者たちの人気を集めた。
美容業界に入れば、美しい男性に会うことは珍しくない。
でも、真也は違った。
初めて目が合った瞬間に、運命だと感じた。
それから、美容のことで埋め尽くされていた私の心に、真也という存在が浸透してきた。
真也への想いが強くなるのと比例して、美しさへの欲望は強くなり、福利厚生でできる施術の頻度が上がるのは当然のことだった。
「三島さん、よかったら今度一緒にお茶でもどうですか?」
真也から声をかけられるまでに、そう長い時間はかからなかった。
真也が私を見る目が、他の従業員と違うことにはとっくに気づいていた。
声をかけられて、飛び出しそうなほど高鳴った心臓の音を隠すことができたのは、事前のイメージトレーニングの賜物だった。
「ありがとうございます。検討させてください」
真也は少し困惑したような表情を見せたが、すぐに笑顔に戻った。
初めて向けられた、私だけの真也の笑顔。
(この笑顔を独占したい)
そう強く思った。
数日後、私は真也と食事をしていた。
真也が私の美しさに見とれているのは、言葉にしなくても伝わっている。
「三島さんは本当に美しい。ほとんど話さないから、最初、本当に人形なのかと思いました」
私は少し口角をあげ、まっすぐ真也を見つめることで、感謝の言葉に変えた。
デートは静かに進んだ。真也が払うと言うので、少しの会話はしたものの、真也が話し、私は微笑むか頷くか。
それでも、真也が私に好意を持っていることは、もう確信に近かった。
帰り道、真也が私の手を取って、低く丁寧に言う。
「三島さん、結婚しよう」
驚きのあまり、思わず「えっ」とコトバを発してしまった。
「君を僕だけのものにしたい」
幸せになれる。そう思ったのとほぼ同時に、返事をしていた。
「はい、お受けします」
やっと、母のように幸せになれるんだ。
結婚後、私は専業主婦となった。真也の収入で十分に生活できる。
朝からゆっくりとヨガで体を整えてから、スムージーを飲むのが日課だ。
「おはよう。美香。今日も綺麗だね」
そう言って、私のおでこにキスをした。真也は私を愛してくれる。
まるでかつての父と母のようだ。
すべての幸せはもう手に入っていた。
妻
当然私も、心から真也を愛していた。
稼ぎもよく、見た目も美しい。家事を強要することもなく、家事はすべて業者に依頼する。
ほしいものはすべて買ってきてくれるし、美容代は真也の施術で無料になった。
もう、コトバ代を節約する必要はない。
(わたしも、真也のために何かしたい)
そう思うのは、自然な流れだった。
(忙しい真也のために、健康的な料理を作ろう)
1人で家にいる時間を、少し退屈に思い始めたころ、真也に提案してみることにした。
「真也、話があるの」
久しぶりに発した声だった。
しばらく聞いていなかったせいで、自分の声だと判断するのに少し時間がかかった。
「どうしたんだい。急に」
「私、お料理教室に通ってみたくて。あなたのために、何かしたいの」
真也は人差し指を口に当てながら、まっすぐ私を見てこう言った
「美香、気持ちは嬉しいがそんなこと考えなくていい。僕は今のままの君を愛している」
今のまま...その言葉に違和感を覚えながらも、愛しているという言葉は、私の心を変わらず満たしてくれた。
愛してる
結婚して5年が経ったころ、わたしは30歳を迎えた。
真也以外の人間とほとんど関わることもなく、美しくあるためだけに生きてきた。
美しい自分。愛してくれる夫。夢に見ていた理想の生活。
真也は毎年誕生日にバラをくれる。歳の数だけ。
今年もきっと大きな花束を持って帰ってくるに違いない。
ウキウキしながら、念入りに髪をとかしていると、玄関が開く音が聞こえた。
真也だ。小走りで玄関に向かう。
「おかえりなさい」
そう言いながら真也を見ると、手には何も持っていなかった。
「お誕生日おめでとう。食事にしようか」
そう言って私を見た真也の目に、一瞬ヒヤリとした。
いつもと雰囲気が違う真也に不安を感じながら、食卓につく。
真也は何も言わない。黙々と、そして丁寧に肉を切り分け、口元に運んでいる。
その姿は5年変わることなく、美しいままだ。
今日は誕生日だというのに。
静かにカトラリーを置き、口元を拭うと、真也はいつも通りの口調で言った。
「今までありがとう。君の幸せを願っている」
真也が何を言っているのか、全く理解ができなかった。
凍りついたように真也を見つめていると、真也は笑顔で続けた。
「離婚しよう」
何を言っているんだろう。今日は私の誕生日だ。変なドッキリならやめてほしい。
「何を言ってるの...」
笑顔を作ってみたものの、自分の声が震えているのがわかる。
「君との生活は快適だったよ。君となら、このまま一緒に歳を重ねられると思っていた。でもやっぱり無理なんだ」
「無理ってどういうこと?他に好きな人でもできたの?」
「いや、違う。美香、君はもう30歳だろう」
「そうよ。今日は私の誕生日なのに、どうしてそんな意地悪を言うの?」
「僕は29歳までの女性しか愛すことができない」
真也は悪びれることもなく、そう言い放った。
私は言葉を理解することができず、ただただ真也を見つめた。
どう見ても、私の見た目は20代にしか見えないはずだ。シワもなく、シミもなく、美しさには自信がある。それなのになぜ。
「施術をして美しさを保っている女性を、たくさん見てきた。でも、違うんだ。年齢という、絶対に技術では変えられない物に価値を感じる、僕にとっては1番美しいのは“若さ”
なんだ」
「そんな、私たち夫婦じゃない。愛し合っているんじゃないの?」
「愛していたよ。若くて美しい君を。君は完璧だった。美しいだけの女性はたくさん見てきたが、コトバを発さないなんて、本当に理想の人形を見つけた気分だったよ」
人形...。確かにそうだ。話さない。ただ毎日そこに美しくいるだけの存在。
「君は僕の、どこを愛してくれていたの?」
真也は冷ややかな目で、そして笑顔で私に聞いた。
わたしは答えることができなかった。
お互いのことは何も知らない。
何も伝えていない。
コトバを交わしてこなかったのだから、当然だ。
私達の間には、最初から心のつながりなんてものは、存在していなかった。
真也は微笑みながら、自分の部屋に戻って行った。
美しさ
真也はわたしに新しい家を与えてくれた。
小さな、1人暮しにちょうどいいサイズの小綺麗なマンションだ。
私が家を出る日も、真也はいつも通り仕事に行った。
「美香、今までありがとう」
私にだけ向けられたその笑顔は、今日からもう私のものではない。
鏡に向かった。そこに映っていたのは、痩せてしまった自分の姿だった。
痩せてしまったせいで、自慢だったハリのある肌も、うるっとした瞳も、ぷるりとした唇も、全て乾いてしまっている。同時に、涙も枯れはてた。
私は静かに呟いた。
「今日も綺麗だわ」
その言葉に、誰も答える者はいなかった。私の前には、孤独だけが広がっている。
ー第3話 終ー
この記事を書いたライター

Nishino
アパレル業界一筋15年。2人の子どもを育てる副業ライター。現在はシナリオライティングをメインに活動中です。おもしろいことが好き!おもしろい人が好き!そんな自分の「好き」を伝えられるライターになりたいです。いえ、なります。
夢は開業...