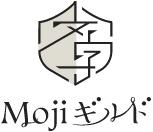夫婦生活
朝日が差し込む寝室で、私は目覚ましの音で目を覚ました。隣で寝ているはずの夫の姿はない。いつもの光景だ。枕に残された僅かな温もりが、夫の存在を物語っている。
リビングに出ると、シンクに置かれたコーヒーカップに触れる。
家を出て30分といったところだ。
自分の分のコーヒーを入れ、パンとヨーグルトで簡単に朝食をとる。
窓ガラスに映る少し年齢を重ねた自分の顔を見つめながら、ふと考える。かつては輝いていた2人の未来が、今はぼやけた風景画のように霞んでいる。
中学2年生で交際を始め、そのままお互いに他の誰かと交際することもなく、結婚した。
付き合いが長すぎて、結婚のタイミングを逃すなんてことはよく聞く話だが、私たちは交際10年でちゃんと結婚した。
そんな私たち夫婦に、子どもはいない。
2人で相談してそうしたわけではない。お互いがキャリアを積み重ねる中で、自然ととった選択だった。
交際した時から似た者同士だった私たちは、熟年夫婦と周りから呼ばれるほどに、阿吽の呼吸で意思決定してきた。喧嘩になったことは一度もないし、お互いの選択に不満をもったこともない。
実際、2人きりの結婚生活に不満はなかったし、お互いの仕事を尊重し合える関係に最初は満足していた。
しかしいつからか、お互いを尊重することと、夫婦としての関係を築いていくことのバランスが取れなくなっていったことに、お互い薄々気づいていた。
一緒に食事をすることもなく、お互いが好きなことを好きなようにして過ごす。
それぞれの自立した生活を、ただ同じ屋根の下で過ごしているだけ。
何かが違うと感じていたが、向き合って解決したいほど大きな問題があるわけでもなかった。
これで不倫だ、借金だと問題でも起きていれば、目を合わせるきっかけになったのかもしれない。しかしながら、私も夫も、真面目だけが取り柄だった。
“何もなければ、足りないものも何もない”
そんな私たちの夫婦生活は、側から見たらどんな関係だったのだろう。
それぞれの
ある夜、夫が珍しく起きて待っていた。
久しぶりに真っ直ぐ私を見る夫の表情で、何を言いたいのかはわかった。
「チエ、離婚しようか」
その言葉は、自然と私の中に流れ込んできて、私の感情と一瞬で混ざり合う。
“なんで?いやだ。別れたくない”
そんな風に言えたら、何か結果は違っていただろうか。
あまりにも自然に私の感情と溶け合ったその言葉は、私の首を縦に下ろした。
「じゃあ、手続きは俺の方で進めるから。何か必要なことは言ってくれ。早く寝るんだぞ」
そう言って、夫は扉を閉めた。バタンという音が少し耳に残ったが、早く寝てしまおうと思った。
余計な感情に、心が飲まれてしまったら、涙が出てしまいそうだったから。
ありがとう
そして、夫婦でいる最後の日まで、私たちはいつもと同じ毎日を過ごした。
離婚の手続きの進捗や、引越しの日程を決めるのは、事務的なテキストのやりとりのみで進んだ。
あっという間に迎えた最後の日の朝、私はあったかい缶コーヒーを飲みながら、窓の外を眺めていた。
私が毎朝ここに座る時間は、近くの小学生が登校する時間で、いつも賑やかだ。子どもたちにパワーをもらってから、出社するのが日課だったのに、これからどうしたものかと思考をめぐらせる。
次の引越し先は、都心を選んだ。できるだけ慌ただしい街で、慌ただしく過ごしたい。なんとなくそう思った。
ぼんやりとして、一向に形にならない思考のまま外を眺めていると、同じように缶コーヒーをもった夫が目の前の席に腰掛けた。
窓側に置いた2人掛けの小さなダイニングテーブルは、引っ越して1番最初に2人で選んだものだ。
お互い、朝はコーヒーを飲むのが好きで、落ち着いてコーヒーを飲めるダイニングテーブルが欲しいとあちこち巡ってやっと探し出したテーブル。
子どもができた時、角が危ないからと丸いデザインの物を探し、長く使えるようにと無垢材を選んだ。このテーブルは、処分することにしたらしい。
あの頃は確かに、お互いが同じ未来をみていたはずなのに。
「…この時間は、子どもたちの声が賑やかだな」
夫がふいに話し出す。
「…うん」
それ以外の返事が見当たらなかった私に、夫は話を続けた。
「俺がここに座る時間は、まだ街が静かなんだよ。少し窓を開けて、ひんやりとした風を入れながら飲むコーヒーがうまかったんだよな」
「だから私が起きた時には、部屋の空気が澄んでたのね」
「寒かったか?」
「いいえ。気持ちのいい朝だなと思っていたわ」
「きっとそう思ってるんだろうなと、思っていたよ」
その言葉に、涙が溢れた。
確かに同じ場所で、同じ空気を感じていたはずなのに、なぜ今日が私たちの別れの日なんだろう。
お互い嫌いになったわけじゃない。お互いの仕事を応援していたし、お互いの価値観を尊重してきた。どうか無理をしないでね。どうか健康には気をつけてね。愛する人に向かう当たり前の感情は、確かに存在していた。
でも、お互い思っていた。もっと言葉を交わしたいと、心のどこかで思っている。そのことから目を背けていた。
長く一緒にいたせいで、話さなくても考えていることはなんとなく、わかっていた。
朝どんな風に過ごしているのか、どんな風に食事をとって、どんなことを思って寝たのか。
だからこそ、いつしか言葉を交わさなくなった。わかりきっていたっていい。
やっぱりそうだよね、で終わってもいい。
それでもよかったのに、できなかった。それがなぜなのかと聞かれたら、うまく言葉にはできないものだ。
沈黙が流れる。その静寂は、言葉にできない多くの想いで満ちていた。
私たちは目を合わせた。そこには、言葉では表現しきれない感情が溢れていた。惜別の情、後悔、そして永遠に消えることのない愛。
今言わなきゃいけないことは、謝罪でも後悔でもない。
でも、今言わなければ、きっと後悔する言葉が確かにある。
私たちは口を開いた。
「今までありがとう。愛してる」
ー第4話 終ー
この記事を書いたライター

Nishino
アパレル業界一筋15年。2人の子どもを育てる副業ライター。現在はシナリオライティングをメインに活動中です。おもしろいことが好き!おもしろい人が好き!そんな自分の「好き」を伝えられるライターになりたいです。いえ、なります。
夢は開業...