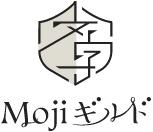夢と金
この世の言葉が有限だからって、誰もが効率良く、自分のためだけに使うなんて、間違っていると思う。
無駄だとバカにされても、何をしているんだと笑われても、その無駄で無謀な誰かのおかげで、私たちは進化し続けてきたんだ。
夜でも街が明るいのも、飛行機が空を飛べるのも、月に旅行ができるようになったのも、誰かが追いかけ続けた夢の果てだ。
ぼくも、そんな偉大な人間になりたい。
無駄だと笑われても、古臭い夢だとバカにされても、自分の夢を必ず実現して見せる。
ぼくの歌で、言葉で、世界中の人に夢と希望のバトンを渡す。そんな歌手になりたい。
3年3組 内田 相馬
歌声
俺は、もう何年もの間、毎週末の夜にこの居酒屋で1人酒を飲んでいる。今日も変わらず、カウンター席に座り、ビールを片手に昔を思い出していた。
かつて俺には夢があった。それは、アーティストになること、歌で人々の心を動かすこと。毎週末、駅前の決まった場所でストリートライブをするのが日課だった。
ギターを抱え、精一杯の思いを込めて歌った。まあ、観客の数は多くなかったが…。
言葉が有限になってから、世の中は大きく変わった。
歌手を目指そうとする人間はほとんどいなくなった。かつてアーティストと呼ばれた人たちの多くは、AIやボカロミュージックに取って代わられた。今やライブができるのは、相当な大物だけだ。
俺の歌手になる夢は叶わないまま、気がつけば45歳。貯金はない。
ストリートライブの場所代、歌う分のコトバ代を払い続けてきたからだ。
恋人もいない。このまま孤独に死んでいくのだろうか。
毎週末、駅前に来る習慣だけは直らず、歌の代わりに酒を飲むようになった。
「すみません、ここ空いてますか?」
ふと、優しい声が耳に入った。顔を上げると、30代後半くらいの女性が立っていた。
おれは無言で隣の席を指差した。
「ありがとうございます」
彼女はカウンターに座り、ウイスキーを注文した。沈黙が流れる。
「あの...失礼ですが、もしかしてSOUTAさんですか?」
突然の質問に、驚いて彼女を見た。
SOUTAというアーティスト名は、親友の健太と考えた名前だ。
相馬として感じるままの言葉をそのまま歌にすればいい。
相馬+歌でSOUTA。
その名前は、ほとんど呼ばれることもなく、この世から消え去ったはずだったのに…
「...どこかでお会いしましたか?」
「いえ、私、覚えてるんです。10年くらい前、駅前で歌ってましたよね?」
俺は言葉を失った。
10年前...まだ夢を追いかけていた頃の自分を、誰かが覚えていてくれたのだ。
「実は、私、毎週あなたの歌を聴いていました。仕事帰りにいつも立ち止まって...」
彼女は少し照れくさそうに笑った。
「本当は、『素敵な歌ですね』って言いたかったんです。でも...」
胸が熱くなるのを感じた。誰かが自分の歌を聴いてくれていた。その事実が酔いを冷まし、熱くなった頭の熱が、胸まで落ちてくるのを感じた。
「ごめんなさい、こんな突然...」
彼女は恥ずかしそうに顔を伏せた。グラスを見つめ、話を続けた。
押された背中
「あの頃、なんだか毎日生きている実感がなかったんです」
彼女のコトバ代が気になったが、自分の歌がどんなふうに届いていたのかを、聞きたい気持ちが勝ってしまった。
「自分が発する言葉は、本当の意味での自分の言葉ではなかった」と彼女は言った。
そうなのだ。言葉が有限になったこの世界で制限されるのは、言葉代という換金できるものだけではない。
「言葉」つまり、自分の気持ちを伝える手段に制限がかかった時、人は良くも悪くも、気持ちを取捨選択しなければならない。
「使う言葉を考えすぎて、本当の自分の気持ちはずっとどこか遠い別の場所にあるような気がしていました」
少し悲しそうにそう言った彼女の気持ちが、俺には手に取るようにわかった。
自分の言葉をどう使うかは、ほとんどの学校では教えてくれない。
自分の価値観を、自分で作り上げていくしかないのだ。
「駅前であなたの歌を聴いていたんです。『未来からの言葉』...その歌詞が、私の心に突き刺さったんです」
10年前に夢を諦めかけた時、自分を励ますために書いた曲だった。
「あの頃から、私は少しずつ前を向けるようになりました。毎週あなたの歌を聴くことで、私が前に進むきっかけになったんです」
彼女の目に涙が光った。
彼女は私の目をまっすぐ見つめ、はっきりとした声で
「あなたの歌が、私を救ってくれました。本当にありがとう」
その言葉を聞いた瞬間、無意識に涙が溢れ出す。
胸の奥で温かいものが広がっていくのを感じた。
歌うたびに嵩んでいくコトバ代を見て、自分の夢を追い続けることが怖くなっていたあの頃の気持ち。
夢を諦めようと決めて、今まで歌ってきたコトバ代は無駄だったんだと、自暴自棄になっていた頃の気持ち。
自分の言葉が、誰かの人生を変えるきっかけになるなんて、おこがましいにもほどがあると、自分の無力さを恥ずかしく思っていたあの頃の気持ち。
その気持ちのすべてが、日に当たったひまわりのように、上を向いていくのを感じた。
あの頃は心から、誰かのためになればいいと、心を込めて歌っていた。
観客は少なくても、親友の健太のように、1人でも多くの人に、バトンを渡せたらいいと願いながら歌っていた。
彼女に何があったのかはわからない。でも、あの頃の彼女の心に、確かに届いていた。
あの時無駄だと思っていた時間が、今度は自分の背中を押そうとしてくれている。
10年の時を経て、自分の歌が誰かの人生を支えていたという事実が、今度は自分を勇気づけてくれている。
彼女は申し訳なさそうに微笑んだ。
「もう一度だけ、あの歌を聞きたいなんていったら、迷惑ですか?」
その言葉に、心の奥底から湧き上がる感情を抑えきれなかった。
長年忘れていた感情が、再び燃え上がるのを感じた。
「もう一度...歌ってもいいんですか?」
俺の言葉に、彼女はただ優しく微笑んだ。
この瞬間、俺は再び言葉を使って歌う勇気をもらった。
たとえ言葉が有限でも、自分の言葉を誰かが未来につなげてくれる。
この歌は、きっと誰かに届く。そう信じて、俺は再び歌い始めた。
久しぶりの歌は、かなり下手くそになっていた。
毎週飲み続けた酒で、喉も焼けている。でも、歌にこめる気持ちは当時のまま。
この歌が、誰かの「明日」を明るく照らす、希望になることを願いながら。
心を込めて言葉を奏でた。
「…ありがとうございます。ずっと、この言葉を伝えたかった」
歌い終わったあと、小さく拍手した彼女は、目尻の涙をぬぐいながら、そう言った。
未来への言葉
その日以来、俺は毎週末、駅前で歌うようになった。
観客は多くはない。働いて稼いだ金は、やっぱりコトバ代でどんどん消えていく。
でも、1人でも心に届く人がいればいい。誰かが明日を歩む、きっかけになればいい。
そう思えるようになった。
言葉は有限かもしれない。使う人それぞれの正義があり、悪がある。
正解は1つじゃないし、答えが見つかることもないだろう。
だからこそ、今日も俺は歌う。未来を信じて、誰かの希望になれることを願って。
ただひたすらに、誰かの未来のために、この言葉を使い続けたい。
〜♪未来への言葉をつないでいこう この先を明るく照らす言葉は 自分自身で灯せるはずだから〜♪
ー第5話 終ー
この記事を書いたライター

Nishino
アパレル業界一筋15年。2人の子どもを育てる副業ライター。現在はシナリオライティングをメインに活動中です。おもしろいことが好き!おもしろい人が好き!そんな自分の「好き」を伝えられるライターになりたいです。いえ、なります。
夢は開業...