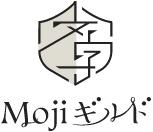朝5時
窓から朝日が差し込むころには、もうすでに目が覚めている。
もう何年も、同じ時間に目が覚めるようになった。
昔は夫が「コーヒーを淹れたよ」と言って起こしてくれたものだが、今はもうそんな声も聞こえない。
今日は私の83歳の誕生日。
夫を5年前に亡くして以来、この家で1人暮らしをしている。
静かな日々。平穏といえば聞こえはいいが、寂しさという感情は毎日のように訪れる。
丸いダイニングテーブルで朝食を済ませ、新聞を読み、庭の草むしり。
昼食を作って食べ、午後はテレビを見たり編み物をしたり。
夕方になると近所を散歩する。そんな毎日。
年金は決して多くはないけれど、質素に暮らしていれば何とかなる。
言葉を使う相手はもういないのだから。
テレビの音声を消して、黙って画面を見つめることもある。
言葉を使わなければ、その分だけお金が残る。
残したところで、今更なにに使うわけでもないだろうと言われることもあるが、勝手に残るのだから仕方がない。
83歳。もう十分に人生を楽しんだ。
今望むのは、誰にも迷惑をかけずに最後まで暮らすことぐらいだ。
お隣さん
夕方、ピンポーンとチャイムがなった。
久しぶりのチャイムに、少し驚いたが、退屈な毎日を過ごしていると宅配便でさえ嬉しく思うことがある。
今日は誕生日だ。少しくらい、誰かと話したい。
がらりと戸を開けると、若い夫婦と小学生ぐらいの男の子が立っていた。
「こんにちは佐伯さん。わたしたち隣に引っ越してきた、山内と申します」
そういえば、今日は朝からトラックが止まっていたが、まさか隣に若い夫婦が来たとは…。
丁寧に挨拶してくれた、どこか都会の雰囲気漂う彼女の言葉を遮るように、大きな声が足元から聞こえた。
「おばあちゃん!ぼく山内健太!7歳!おばあちゃんは何歳?」
こら!健太!と注意されていたが、そのパワーに思わず笑みが溢れた。
「健太くんて言うの。佐伯チエです。今日で83歳になったわ。これからよろしくね」
そういうと、健太は目をまんまるにして大はしゃぎでこう言った。
「チエばあちゃん今日お誕生日なの!?じゃあ、パーティーしなきゃ!僕のお家においでよ!お母さん、いいでしょ!?」
「何言ってるの!あんな散らかった家に、お招きできるわけがないでしょう!佐伯さん、せっかくのお誕生日にお邪魔してしまってすいません」
お誕生日パーティー。そんなことを言われたのは、生まれて初めてだ。
中学からの同級生だった夫との間に子どもはいなかったが、子どもは昔から好きだった。
毎日仕事前に見かける、小学生の子ども達を見ては、パワーをもらっていたが、まさかこの年になって子どもと交流できるとは…。
「いえいえ。そんな風に言ってもらえてとても嬉しいわ。健太くん、ありがとう」
健太は、誕生日パーティーができないことをブツブツと怒っていたが、夫婦は構わず話を続けた。
「私たち、共働きで…。帰りが遅くなることもあって。健太が1人で家で過ごすことも多いので、その…やかましいかもしれないのですが…」
「気にしないでください。一人暮らしで毎日寂しいから、賑やかなぐらいでちょうどいいです」
そう言ったのは本心だった。夫婦は、何かご迷惑をかけたら言ってください、と言いながら、不貞腐れた健太を無理やり家に連れて帰った。
久しぶりに賑やかな時間を過ごした。何よりの誕生日プレゼントだ。
子どもからパワーをもらう体質は変わっていない。いつもより念入りに、シンクを掃除した。
小さな友人
その日から、隣の家の様子が気になって仕方がなかった。
朝早くに出かけていく両親。夕方遅くに帰ってくる姿。
そして、1人で留守番をしている健太。
健太は最初の頃の印象と変わらず、ずっと元気で明るい男の子だった。
会えば元気に挨拶をしてくれるし、チエおばあちゃんと呼んでくれるその笑顔が可愛かった。
ある夕方のこと。
散歩から帰ってくると、隣の家の前で健太が1人で座っていた。
「こんにちは」
声をかけると、健太は少し驚いたような顔をしたが、すぐに笑顔になった。
「こんにちは、チエおばあちゃん!家の鍵忘れちゃってさ。家に入れないんだよ」
健太は少し不安そうな感情を隠すように、笑顔でそう言った。
おせっかいかと思ったが、家で待っているかと尋ねると、満面の笑みで
「行く!!!!」
と答えた。
健太は本当にかわいい男の子だった。
学校であったこと、引っ越してくる前の友達の話、テレビの話や音楽の話、コロコロと表情を変えながら話すので、こっちまで笑顔になってしまう。
おやつを食べながら過ごした時間があまりにも楽しく、あっという間に夕方になった。
母親が何度も頭を下げたが、お礼を言いたいのはこちらの方だ。
「チエばあちゃん、また来ていい?」と健太がいうので
「もちろん。おいしいおやつを準備しておくね」と答えた。
こうして、83歳の私に、歳の離れた7歳の友人ができた。
有意義
その日から、自然と夕方の時間を一緒に過ごすようになった。
最初はコトバ代のことが気になって、健太の話をうんうん、と聞いていた。
でも、健太の無邪気な笑顔を見ていると自然と言葉が出てくる。
「おばあちゃん、今日ね、学校で相馬くんがね...」
健太の話を聞きながら、私は幸せを感じていた。
久しぶりに、誰かと会話を楽しむ喜び。
コトバ代のことなど、どうでもよくなっていた。
日々が過ぎていく。健太との時間が、私の生きがいになっていった。
年金は日に日に減っていくが、心は満たされていく。
コトバ代の有意義な使い方が、やっとわかった気がした。
83歳。長い月日がかかってしまったが、人生の終わりを迎える前にこの気持ちを知ることができて、本当によかった。
終わりあるもの
私の人生の終わりは、もうすぐそこまで来ていた。
夫が亡くなってしばらくして見つかった病は治療する選択をせず、夫のところにいく準備期間にすることにしていた。
しかし、健太と出会ってしまったことで、感情に変化が起きてしまった。
健太と話したい。健太のためにおいしいものを準備したい。
でも、わたしには終わりが近づいている。
私がいなくなったら、健太は悲しむだろうか…。
そんなことを考えるようになっていった。
健太のために、自分は何ができるか。
そう思うのと同時に、もう健太と話せなくなる。
その現実が、胸を締め付ける。
(ねえ、私ができることって何かしら…)
返事のない夫に語りかけながら、83年の人生を振り返る。
自然と眠りについた時には、もう朝日が昇ったころだった。
翌日、夫の写真を見返しながら、心を決める。
最後に、私ができること。健太にちゃんと伝えよう。
コトバ
いつものように健太がやってくる。
たわいもない話を聞いて、いつものように涙が出るまで笑う。
なんて幸せな時間だろう。
「健太、今日はおばあちゃんも話したいことがあるの」
健太は不思議そうな顔をした。
「おばあちゃん、健太に会えて本当に嬉しくて幸せだわ。ありがとう」
急に何を言い出すのかと思っているのが、表情でわかる。
私は深呼吸をして、精一杯の思いを込めて言葉を紡いだ。
「言葉は有限よ。でも、伝えないと伝わらない大切なことが、この世にはたくさんあるの」
健太は黙って私の言葉を聞いていた。
「どんなに愛し合っていても、どんなに一緒にいても、言葉は渡さないと受け取ってもらえないの」
「渡す?」
健太は首を傾げた。
「そう。言葉は目に見えないけれど、相手に渡す物なの。大切な人には、素敵な物をあげたい、おいしいものを食べさせてあげたいと思うでしょう?どんなに素敵なプレゼントでも、相手に渡さないと、意味がない。食卓に並べないと食べてもらえない。それと同じなの」
「なんか難しいけど、なんとなくわかるよ!」
健太の返事にクスッと笑う。
「いつかわかるわ。健太は優しい子だから」
そう言って、深呼吸をしてから、最後の言葉を伝えた。
「わたしから、健太に言葉のバトンを渡すわ。健太、本当にありがとう。あなたのおかげで、私は本当に幸せな時間を過ごせたわ。健太もいつか、この言葉のバトンを、大切な人に渡してちょうだい」
そういうと、健太はキラキラした笑顔でこう言った。
「言葉を渡すって素敵だね!じゃあさ、おばあちゃん!僕のバトンも受け取って!僕、おばあちゃんのことが大好き!おじいちゃんにバトン渡せる?天国にいたら渡せない?おばあちゃんの大切な人、おじいちゃんだもんね?大好きって伝えられる?」
結局最後まで素直に夫に伝えられなかったバトンを、健太がくれた。
涙をハンカチで抑えると、健太が背中をさすってくれる。
83歳。もう十分に幸せな人生だった。
今望むのは、目の前にいる健太の幸せだけだ。
夫に会ったら、必ず言葉のバトンを渡そう。大好きだよと。
ー第7話 終ー
この記事を書いたライター

Nishino
アパレル業界一筋15年。2人の子どもを育てる副業ライター。現在はシナリオライティングをメインに活動中です。おもしろいことが好き!おもしろい人が好き!そんな自分の「好き」を伝えられるライターになりたいです。いえ、なります。
夢は開業...