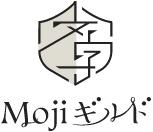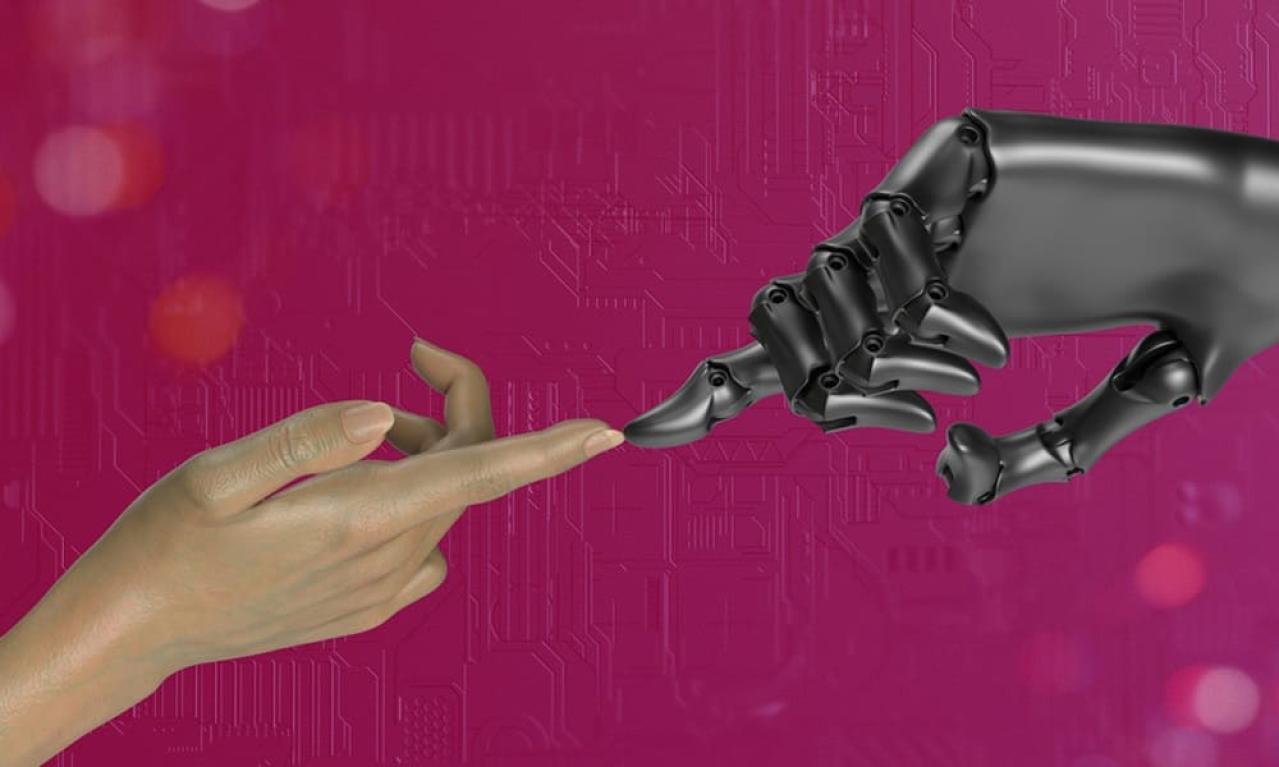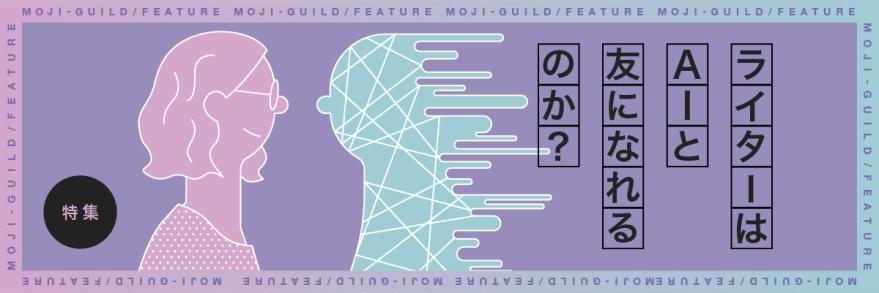そもそもシンギュラリティとは

シンギュラリティとは日本語で「技術的特異点」と訳されます。
ざっくり言えば、AIの知能が人間の脳と同等の性能を持つようになるタイミングのことだと考えられています。
これだけではいったいなにがシンギュラリティなのか、わかりづらいですね。
実はなにを持ってシンギュラリティとするのかは、明確な定義はありません。ただ、ひとつの基準として「AIがAIを開発する」という状況を挙げている研究者が多いようです。
「AIがAIを開発する」ということは、機械が目的意識を持って自発的に行動する、と理解することができます。
では、自発的に考えるとはいったいどのような行動を指すのでしょうか。これには2つの行動があると考えられます。
一つは与えられた業務の中で、効率化のための新たな発想を実現すること。もう一つはすでにストックしている情報の中から命令なしに行動すること。
前者はあくまでインプットされた情報に対するアウトプットであり、数ある情報の中の最適解を選んでいるだけで、シンギュラリティだとは言えないと思います。
後者は自我がなければできない行動です。つまり自らが願望を持ち、それを叶えるための行動を取るという状態です。
どちらかといえば、後者がシンギュラリティに近いものではないでしょうか。つまり、シンギュラリティでいう人間の脳と同等という状態は、感情を有するか否かだと解釈することができるかもしれません。
シンギュラリティは起こり得るのか

学者さんの中でも起こるか起こらないか意見が割れているシンギュラリティですが、個人的な意見を言わせてもらえば、シンギュラリティが感情を持つことを指すことだと仮定するのなら、やってこないと考えています。
夢のない男で申し訳ございません。でも、その理由は以下でしっかりとまとめますので、ご容赦ください。
理由1:感情は効率化と正反対
AIにしろ機械にしろ、その開発の目的は作業の効率化にあるはずです。なぜ、機械で代替するかといえば、疲労がなく、睡眠も必要とせず、さらに気分によるモチベーションの波もなく安定的に仕事を行えるからでしょう。
そう考えると、感情を持つ機械やAIは効率化の反対に位置するものだと思われます。そのようなものを開発する意味は果たしてあるのでしょうか?
理由2:到達点が人間だとは思えない
こうしたAIの議論の多くで、終着点を人間と考えている節があるように思うのですが、前述のようにAIの存在意義を考えると、どうしても終着点が人間のように思考することではないと感じてしまいます。
効率性を考えていけば、どんどんムダや工程を削ぎ落とした特化型のAIこそが理想だと感じるのは私だけでしょうか。
確かに感情というものがあるからこそ、人間はここまで進歩し、文化を形成できたのだとは思います。しかしながら、AIはどれだけ便利であろうとあくまで道具です。道具の本来あるべき姿は使う用途に特化した姿だと、自分は考えます。
ターミネーターの世界に興奮しないわけではないですが、制御不能の道具なぞ道具としての意味をなしてないですよね。
文章生成AIのシンギュラリティ

では、AIのシンギュラリティを感情を持って、自発的な行動を起こすことだと仮定するのなら、文章生成AIのシンギュラリティが仮に起きたとして、どんなことが実現されるでしょうか。
文章生成AIは汎用型AIではなく特化型のAIになるため、AIの開発を実行することはないと思われます。そうなると、起こり得ることとしては、以下のようなものが考えられます。
- インプットされている情報を取捨選択し、自分なりの意見を有するようになる
- エッセイや日記、意味のないツイートなどを自動的に行えるようになる
- 小説や短歌、詩などを一単語のテーマのみで生成可能になる
AIが反対意見を論じたり、独り言のような言葉を話したり、文化的な活動を行うことができるようになる、という状態ではないかと思います。
しかし、一見すると感情がなければできないことのようにも思えますが、AIの性能が上がれば十分に可能なことだと思っています。
自分なりの意見=制作者の意見としてインプットすれば、さも自身の考えを話しているような原稿は作れますし、エッセイや日記もテーマと設定を与えれば可能でしょう。小説や詩などはある程度の定型もできてきているので、すぐに実現できるのではないかと思います。すでに小説のプロット作成や、それっぽい文章の生成は行えているとも聞いています。
結局のところ、人間の感情の発生要因などはわかっていなくても、アウトプットとしての感情はある程度パターン化することはこのご時世、きっと可能なはず。そうなると、なおのことツールに感情をもたせる必要性はなくなっていくのではないかと思います。
AIの表現の幅は今後も広がっていくことが予想されますが、それはあくまでツールとしての範疇に収まるものでしかありません。制御できる以上、AIが人間の、そしてライターの敵になることは今後もないと思いますので、みなさん、安心して仕事をしていこうではありませんか!
この記事を書いたライター
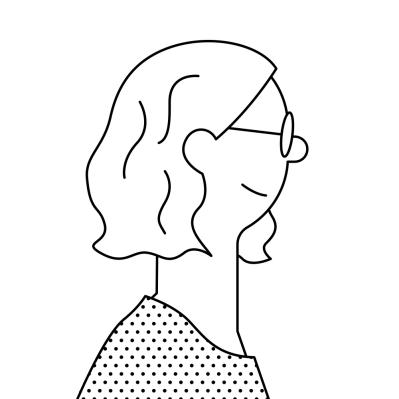
じょん
一児の父でアラフォーライター。
Web制作会社にてライターとしてのキャリアを積みながら、副業ライターとして活動中。得意分野はエンタメ系。興味のある分野では作成する文章にも地が出がち。座右の銘は「ライターは文化的雪かき」。鈍く光る職...